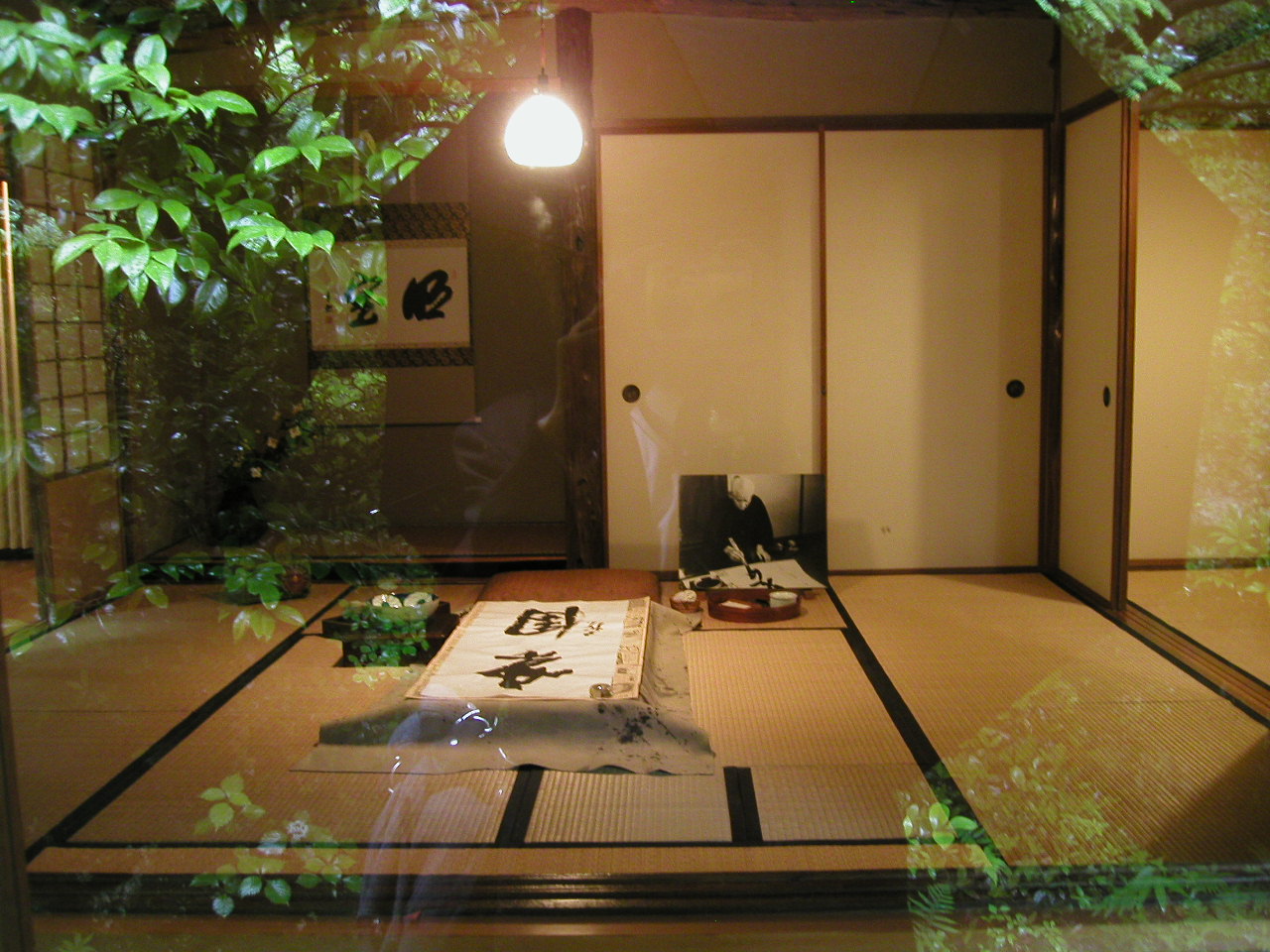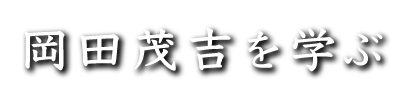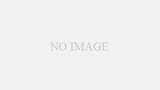メシヤについて、出版部客員松井誠勲氏が該博なる蘊蓄の下に次号に詳細解説される事は喜びに堪えないのである、無論読者もメシヤの起源を知りたいと渇望しているに違いないからである、勿論私と雖も右によって初めて知った位であるが、そのようなアヤフヤな考えで救世(メシヤ)教の名を冠したのは軽率と思うかも知れないが、それについて述べてみよう。
いつも言う通り、私は神の啓示によって具体的に表わすのであるから救世(メシヤ)教の名もそうであって、神様から救世教の名の啓示があったのである、しかし救世教では漢字であるから東洋に限られる、どうしても全人類を救うにはそれに相応する意味を表わさなければならない、それが為、救世(メシヤ)のフリ仮名を付けたのである。
以上の意味であるから、メシヤとは救世の意味だけであって、今後の活動に適合する為のもので他に意味はないので其事をここに断わっておくのである、人によってはキリスト教に関係のある名称だから、時局便乗主義からと思うかも知れないが、そういう点は些かもないのである。
*以下新聞記事詳細
メシヤ(救世主)について 松井誠勲
『救世』51号、昭和25(1950)年2月25日発行
メシヤとはアルメニア語であります、ギリシャではキリストと訳し、わが国では救世主と訳します。今では専ら神の使命をうけてこの世に降臨し、人を救い世 に平和祐もたらす者の意味に使われていますが、この語はもともと「主より膏を注がれる者」の意味で、イスラエルの古い習慣に、主の即位式には頭に膏を注い だことがあり、それから来た名称であります。その後いろいろの意味に使用され旧約聖書の中には、三十度も使われていますが、ある時は王の意味であり、ある 時は司祭、ある時は族長を意味し、甚だしきはシルス大王を指している場合さえあります。しかし従来は神の使者として審判を行うため、この世に現れる者の意 に用いられ、世界の終末観と関連して考えらるるのが普通でありました。
しかしそうした意味に使われているのは旧約聖書の中ではただ一度ダニエル書第九章に見えておるだけであります。しかもそれは総てを焼き滅ぼす火をもたら す者であろうか?あるいはまだ尽くることのない天与のパンをもたらす者であろうか?誰にもわからないが、イスラエル=ユダヤ人等はこれを自分に都合よくメ シヤの出現はイスラエルに不幸の終りを意味すると解釈して、メシヤの出現をあたかも大旱に雲霓を望むがごとくに待ち焦がれているのであります。そしてその 希望と期待が、一般的であったことは、福音書の到るところに散見することが出来ます。即ちフアリザイ人も一般人も司祭も皆いつかはがかるメシヤが来臨する と信じて疑わず、常に一様に語り合っていることが窺われます。それはヨハネの言葉の聴聞者達がヨハネネに発した第一問が「汝はメシヤなりや否や」であった ことによっても知ることが出来るのであります。
かくメシヤを渇望するイスラエル人は聖書の文章について、メシヤの何人なるかを探し求め、種々と想像を逞うした結果、彼らの脳裏にえがいたメシヤは、武 将の面影でもあり王様の姿であり、それぞれの想像に基いて詩となり、文章となって広く人口に膾炙されるようになったものと思われます。律法の師伝註釈ダル ダムは「何と美しきよニダの家より出づる王なるメシヤ、彼は腰に帯して荒野を征き、敵に戦いを挑み、玉達を滅ぼす」と言い、紀元前一世紀の頃の偽書「ソロ モンの詩」には「メシヤは聖なる民を正義の座に集め祝せられたる十二族を掌らん、メシヤは民に不正を残さず、その傍らに悪者なからん、神はその民に聖なる 心を強め、叡智の賜物に富ましめ給うたればなり。この時生くる者は幸なるかな、彼らに歓喜につどう、イスラエルの十二族を見るべし」と言うがあり、また中 にはイスラエル民族が異国民より絶えず迫害された恨みをメシヤによってはらさんとの希望を表現したもの「鉄塊を以って諸国民を粉砕し」「素焼きの壷のごと くこれをこぼち、彼ら頭を打ちつぶし」「広大な国々に死骸の山を築き」[敵の胸に鋭い矢を突き立てる」=詩篇第二、第二十、第四十五=等があります。しか し聖書の中には恥しめられ苦しめらるる罪の贖主としてのメシヤの姿も現われており、更にその苦しみと死を世界の救いのために与える救い主としてメシヤの姿 も描かれてあります。殊に注目すべきはイザヤ書の章句にはそこに既にカルクリオ山におけるキリスト姿がそのままに誌るされてあることであります「彼は世に 軽んぜられ棄てられ給いぬ。苦しむ人、常に悩む人、その面前に立てば人顔をそむく、我ら蔑みて一顧を与えず」「人彼を悪しざまに扱い、彼従順に苦しみに服 し給う。彼は口を開き給わず、屠場ににひかるる羊、毛をかり取る人の前に黙する小羊のごとし…彼は迫害と裁判に曝され給えり」=イザヤ書五十三章=
メシヤについてはかように「勝利者たる武将または王者の姿」と「犠牲の子羊の姿」とが旧約聖書の中に描き出されてあり、幾度か重なる迫害に悩みいるユダ ヤ人らが、前者のメシヤを期待したことは是非なきことと言わねばなるまい。しかしながらそれがためメシヤの真の姿が曲解されて世に紹介されたことはまこと に遺憾であります。
かくして彼らイスラエル=ユダヤの人々は征服者たるメシヤを待望しながらその希望の中にあらゆる不遇と闘い、度重なるる迫害に耐えて暮して来たのであり ます。さればヨルダン河畔に現れたヨハネを見た彼らはヨハネの口から神の言葉を聞かんとして八方より集り来たったばかりでなく国の権威者、大司祭等も調査 のため現地に公式の委員を派遣してヨハネに質問したのであります。そしてその質問の第一は前に述べたごとく「汝はメシヤなりや」であったのであります。こ れに対してヨハネの答え「否、我はメシヤにあらず」であり「我は預言者イザヤの言いしごとく、汝らの道を平にせよと野に呼ばわる者の声なり」であった=ヨ ハネ伝第一章=またヨハネは「されど我に優りて力あるもの将に来たらんとす、我はその履の紐を解くにも足らず…彼の手に箕ありて、その秣場を潔め殻は消え ざる火にに焼き給うべし」=ルカ伝第三章=とも言われた。ヨハネは更に「改悛」の尊ぶべきを説き「愛」や「正義」や「平和」を教えた。そしてこれらの言葉 はイスラエル人は従順に受け納れたのであるが、前に述べたヘブライ人の自負心を打ち砕くごとき言動には彼らユダヤ人は全く落胆したのであります。
しかるに預言者ヨハネの言葉を聞かんものと寄り集った群衆の中にイエスがいてヨハネに近付いたのでありますが、ヨハネに一種の霊感がひらめいたか、ヨハ ネは身をさけてイエスに向って「我こそ、汝に洗せらるるべきに、汝、我に来り給うか」と言って洗礼を拒んだところイエスは「姑らくそれを許せ、かく我らが 正しきことを恙く悉く遂ぐるは当然なればなり」=マタイ伝第三章=と言いて、ついにヨハネから洗礼をうけたのであります。その時、聖霊は鴿の形で天から舞 い降り、川から上って来る者の上に止るのが見られた。また、天は開けそこから高らかに響く声が聞かれた「これぞ、我が心を安んぜる我が愛子なる」=マタイ 伝第三章=∃ハネ伝第一章=
イエス時に齢三十だったと伝えられ、それからイエスの伝導が開始されるのであるが、ヨハネに失望したユダヤ人からの久しく待望したメシヤをイエスに求 め、非常な関心をイエスに寄せ、これに従って教えを聞くに至ったことは新約聖書に示されてある通りである。しかしイエスはユダヤ人の心に描いていたごとき 異民族を征服する武将でも王者でもなく、イエスの眼中にはユダヤ人もその他の人々も一視同仁で、もっぱら神の愛を述べ、征服どころか「左の頬を打たんとす る者には右の頬をも向けよ」と教えて柔和と平和を唱えたので、彼ユダヤの人々はまたもや失望し、憤慨して遂にイエスを十字架にかけるに至ったことは誰もが 知るところであります。
以上述べるごとくイスラエル=ユダヤ民族の待望したメシヤは、昔の大王ダビデやソロモンのごとく、イスラエルを再興して鉄の杖を以って異邦人共を治むべ き国民的英雄の出現であった。彼らはかかる人物がメシヤとしてこの世に降臨するであろうことを脳裏に描いてひたすら待ち焦れていた。従ってヨハネのごとく またイエスのごとく、イスラエル人が神の選民たることを否定し、世界人類を平等視し等しく神の愛を以って抱擁しようとした態度に失望し、落胆し、憤慨し果 ては極悪の盗賊を詐してもイエスを十字架にかけよと絶許し、強要して遂に死刑に処せしめたのであります。しからばイエスはメシヤではなかったのであろう か?イエスをメシヤなりと信ずる者は言う、イエスは予言者イザヤによって示されたメシヤそのままの姿であり、そのままの経路をたどったではないか、これが メシヤでなくて何んであろうと、イエスを真のメシヤなりと説く者にはイエスの再臨を説く者が多い。即ち世界を審判すべき権能を以ってイエスが再びこの世に 来臨すると言うのであります。この事は聖書の中にも誌るされてあります。聖パウロがその日「主イエスあたりに燃ゆる焔にかこまれ、彼の能力を宣する天使等 と天より現れん」と述べておるのがその一例であります。またある者は言う、イエスはメシヤではないが、やがて来たるべきメシヤを啓示するために神より遣わ されたものである。真のメシヤ、世界の終末に当り、降臨し来って審判を行うであろうと。これらの議論は二千年の久しきにわたって盛んに行われ、まことに諸 説紛々で今ここにこれを詳述することは出きないのであります。
https://www.rattail.org よりご了解をいただき転載させていただきました。
感謝申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~以下自分で途中まで文字起こしした内容です。結構な時間と手間がかかったので消し難くまだ残しています。(笑い)
時間のある時にどこが出来なかったのか勉強させてもらいたいと思っています。八尾屋
メシヤ(救世主)について(救世51号 昭和25年2月25日発行)一部抜粋
松井 誠勳
メシヤとはアルメニア語であります。ギリシャ語ではキリストと*譯し、わが国では救世主と譯します。今では専ら神の使命をうけてこの世に降臨し、人を救い世に平和をもたらす者の意味に使われていますが、この語はもともと「主より膏を注がれる者」の意味で、イスラエルの古い習慣に、王の即位式には頭に膏を注いだ事があり、それから来た名称であります。その後いろいろの意味に使用され旧約聖書の中には三十度も使われていますが、ある時は王の意味であり、ある時は司祭、ある時は族長を意味し、甚だしきはシルス大王を指している場合さえあります、しかし従来は神の使者として審判を行うため、この世に現れる者の意に用いられ、世界の終末観と関連して考えられるのが普通でありました。
しかしそうした意味に使われているのは旧約聖書の中では只一度ダニエル書第九章に見えてをるだけであります。しかもそれは総てを焼き滅ぼす火をもたらす者であろうか?或いはまた盡くることのない天与のパンをもたらす者であろうか?誰にもわからないが、イスラエル=猶太人等はこれを自分に都合よくメシヤの出現はイスラエルに不幸の終わりを意味すると解釈して、」メシヤの出現を恰も大旱に雲霓
を望むが如くに待ち焦がれていたのであります、そしてその希望と期待が、一般的であったことは、福音書のいたる所に散見することができます。即ちファリザイ人も一般人も司祭も皆いつかはかかるメシヤが來臨(らいりん)すると信じて疑わず、常に一様に語り合っていたことが窺われます。それはヨハネの言葉の聴聞者たちがヨハネに発した第一問が「汝はメシヤなりや否や」であったことによっても知る事が出来るのであります。
かくメシヤを渇望するイスラエル人は聖書の文章について、メシヤの何人なるかを探し求め、いろいろと創造を逞しうした結果、彼らの脳裏にえがいたメシヤは、武将の面影でもあり王様の姿であり、それぞれの創造に基づいて詩となり、文章となって廣く*人口に膾炙(ひとぐちにかいしゃ)されるようになったものと思われます。律法の師傳註釈ダルダムは「なんと美しきよユダの家より出づる王なるメシヤ、彼は腰に帯して曠野を征き、敵に戦いを挑み、王達を滅ぼす」と言い、紀元前一世紀の頃の偽書「ソロモンの詩」には「メシヤは聖なる民を正義の座に集め祝せられたる十二族を掌らん、メシヤは民に不正を残さず、その傍らに悪者なからん、神はその民に聖なる心を強め、叡智の賜物富ましめ給うたればなり、この時生くる者は幸なる哉、彼らは歓喜に集う、イスラエルの十二族を見るべし」と言うがあり、また中にはイスラエル民族が異国民より絶えず迫害された恨みをメシヤによってはらさんとの希望を表現したもの「鉄兜を以って諸国民を粉砕し。」「素焼の壺の如くこれをこぼち、彼らの頭を打ち潰し」「廣大な国々に死骸の山を築き」「敵の胸に鋭い矢を突き立てる」=時篇第二、第二十、第四十五=等があります、しかし聖書の中には恥ずかしめられ苦しめらるる罪の贖主としてのメシヤの姿も現われており、更にその苦しみと死を世界の救いのために與える救い主としてメシヤの姿も描かれてあります、殊に注目すべきはイザヤ書の章句にはそこに既にカルクリオ山に於けるキリストの姿がそのまま誌るされてあることであります。「彼は世に軽んぜられ棄てられ給いぬ、苦しむ人、常に悩む人、その面前に立てば人類をそむく、我等蔑みて一顧を與えず」「人彼悪しざまに扱い、彼従順に苦しみに服し給う、彼は口を空き給わず、屠場に引かるる羊、毛を刈り取る人の前に黙する子羊の如し….彼は迫害と裁判に曝され給えり」=イザヤ書五十三章
メシヤについてはかように「勝利者たる武将または王者の姿」と「犠牲の子羊の姿」とが旧約聖書の中に描き出されてあり、幾度か重なる迫害に悩み憤るユダヤ人等が、前者のメシヤを期待したことは是非無き事と言わねばなるまい、しかしながらそれがためメシヤの真の姿が曲解されて世に紹介されたことは是に遺憾であります。
かくして彼等イスラエル=ユダヤの人々は征服者たるメシヤを待望しながらその希望の中にあらゆる不遇と闘い、度重なる迫害に耐えて暮してきたのであります。さればヨルダン河畔に現われたヨハネを見た彼らはヨハネの口から神の言葉をきかむとして八方より集まり来ったばかりでなく国の権威者、大司祭等も調査の為現地に公式の委員を派遣してヨハネに質問したのであります。そしてその質問の第一は前に述べた如く「汝はメシヤなりや」であったのであります。一これに対してヨハネの答えは「否、我はメシヤにあらず」であり「我は予言者イザヤの言いし如く汝らの道を平らにせよと野に呼ばわる者の聲なり」であった=ヨハネ傳第一章=またヨハネは「されど我に優りて力ある者将に来らんとす、我はその履の紐を解くにも足らず…彼の手に箕ありて、その祩場を潔め殻は消えざる火にて焼き給うべし」=ルカ傳第三章=とも言われた、ヨハネは更に (後略)
*譯し….訳し
*人口に膾炙...人々の話題に上ってもてはやされ、広く知れ渡る。
ーーーすみません。大変申し訳ありませんが、わからない文字、判然としない文字が多く、勝手ではございますが以下省略させていただきました。以降の文も大変大事な内容と思われます。(汗)
概略でも新聞紙面を拡大して、お読みいただくことはできます。
また、キチンと文面を読み取れる方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただけましたら幸いです。
八尾屋