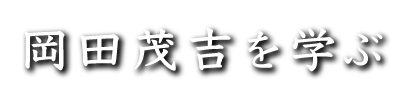パウロのことについては、前にも少し触れましたけれど、ここで更にもう一度取上げる理由は、パウロ研究をぬきにしてはキリスト教の本質を論ぜられないとされておる程に、パウロの存在がキリスト教にとって密接不離の関係に立っているからなのであります。
パウロはユダヤ人であり、そのユダヤ名はサウロと呼ばれておりました。彼はローマの市民権を持っておりましたが、それは彼の父祖がローマ帝国に対して示した忠誠の結果であったろうとされております。
そのローマ市民権というのは当時なかなか獲得出来ないものであったのですが、彼がそれを生まれながらにして持っておったこと、更にその家庭がギリシア・ローマ文化世界における華やかな一大商業都市タルソにあったことなどは、彼の生涯に注目すべき意義をもたらしていることを見逃がすことができません。彼の書簡を通して見ても、都会の雑沓の中に人となったパウロは、ガリラヤの山々や、森や湖のような自然の環境に成育したナザレのイエスとは随分異っております。彼の使う譬喩(ひゆ)を見ても、建築であり、法廷であり、奴隷の売買などであったことから推して、都会的環境がいかに彼の脳裏に浸み込んでいたかが窺われるのであります。ですから彼が幼少より接触したギリシア的なものが、彼の内的生活に影響しておったことも勿論でありましょう。
当時のローマ市民は、ユダヤ律法の行者としての厳格な責任を負わされていたのであって、パウロもまたその選にもれなかったわけであります。それどころか、パウロは律法に全生命を捧げ尽すまでの熱意を有する一人であったのであります。
ステパノは、ユダヤ教の中心問題である神殿礼拝と、それを基礎づけている律法とについて鋭い批判を加えて、神殿礼拝は既にその意義を失ったのだと主張し、更にナザレのイエスを十字架にかけたことによって、ユダヤ人は律法を踏みにじったと指摘しました。このことはパリサイ人にとっては、心臓をえぐられる思いであったことでしょう。殊に彼らはナザレのイエスをメシア(救世主)として仰ぐキリスト教徒の態度が神を冒涜するの甚しいものであるとして看過し得なかったのでありました。つまり彼らは約束のメシアが、エノク書に誌されたり、ソロモンの詩篇に歌われたりしているように、王者としてか、勝冠をかぶった将軍として来るものだと信じていたので、十字架にかけられたメシアなどは到底思いもよらなかったに相違ないのであります。そして遂に彼らは、メシアを宣伝するキリスト教徒を敵として戦うことを決意したのでありまして、パウロは実にその指導者となったのであります。
このようにして、パウロは迫害の炎を燃やしながらダマスコに追跡の手をのばしたのであります。「往きてダマスコに近づきたるとき、忽ち天より光いでて、彼を環り照したれば、かれ地に倒れて『サウロ、サウロ、何ぞ我を迫害するか』」との声を聴いたのであります。彼は、「主よ、なんぢは誰ぞ」と尋ねた。答えは「われは汝が迫害するイエスなり。起きて町に入れ、さらば汝なすべき事を告げらるべし」というのでありました。同行の人々も声を発することが出来ずに、ただ呆然として佇立(ちょりつ)したままでありました。彼らはいずれも姿こそ見ませんけれども、その声は確かに聴いたのであります。「サウロ地より起きて目をあけたれど何も見えざれば、人その手をひきてダマスコに導きゆきしに、三日のあひだ見えず、また飲食(のみくい)せざりき」(使徒行伝第9章参照)
この驚くべき出来事の間に、パウロは栄光かがやくイエスの姿をはっきりと認めたと言うのであります。「光、暗より照り出でよと宣(のたま)ひし神は、イエス・キリストの顔にある神の栄光を知る知識を輝かしめんために我らの心を照し給へるなり」(コリント後書第4章)と彼自ら誌るしておるのであります。これを、甦りて神の右にたち給うキリストが、彼を捕えて方向転換を行わしめたところの神の導きであると考えて、彼が従来反抗し、迫害し続けてきたイエス.キリストに対し、彼は絶対的に服従する人となったのであります。これこそ彼にとっては、「最早われ生くるにあらず、キリスト我が内に在りて生くるなり」(ガラテヤ書第2章)なのであります。
パウロは、「キリストの愛我らに迫れり」との歓喜に満ちて、かつまた狂気せんばかりの熱情を以ってこの事実を宣べ伝えるために彼の全生涯を捧げつくした観があります。
だからこそパウロは、「わが労は更におほく、獄(しもと)に入れられしこと更に多く、鞭うたれしこと更に彩だしく、死に瀕みたりしこと屡次(しばしば)なりき。ユダヤ人より四十に一つ足らぬ鞭を受けしこと五度、笞(しもと)にて打たれしこと三たび、石にて打たれしこと一たび、破船に遭ひしこと三度にして一昼夜、海にありき。しばしば旅行して河の難、盗賊の難、同族の難、異邦人の難、市中の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難にあひ、労し、苦しみ、しばしば眠らず、飢え渇き、しばしば断食し、凍え、裸なりき。ここに挙げざる事もあるに、なほ日々われに迫る諸教会の心労(こころづかい)あり。誰か弱りて我弱らざらんや、誰か躓きて我燃えざらんや」(コリント後書第11章)と告白しておるのであります。
しかもそれはカイザリア幽囚や、ローマ幽囚の前なのでありまして、このような苦難も遂にパウロの鉄石心を砕く事が出来なかったことを雄弁に物語っております。
更にパウロについて特筆すべきことがあります。それはそもそも、キリスト教が国境や民族を超えて伝播されるようになってまいりますと、次のような問題に出会わねばなりません、つまりキリスト教はユダヤ教内のキリスト教であるのか、あるいはユダヤ教に対立するものとしてのキリスト教であるのか。そして又律法の内にあって律法と併立する信仰であるのか、あるいは律法に対立している信仰なのか、などという問題がそれであります。ところがこれに対してペテロとかヨハネとかははっきりした態度をとっておりませんでした。このときに当って、パウロはキリスト教信仰独自の位置を主張して、律法ではなく、キリスト・イエスを信ずる信仰においてのみ救われるのだということを開明しました。この点はパウロについて語るとき、忘れてはならないのであります。
この一事の外更にパウロの持つ意義の重要な点は、ヘレニズム(汎ギリシア主義)諸宗教の神秘主義と汎神的な敬虔さに対して、敢然として唯一神観をどこまでも把持し通したことであります。パウロは、神は創造者であって、造られた世界と混同することの出来ない超越者であるとするのであります。
パウロの生きていた当時においてすら、このような意味での唯一神観がユダヤ教などの宣伝を通して、ギリシア・ローマの人々に知られていなかったわけではありません。けれども一般の人々が抱いていたのは、やはりギリシア的な汎神的神観であったと言えましょう。これらの人達が抱いていた汎神観は、美しく、また秩序正しく決定されている法則の中に動く世界それ自身が神だとするのであります。また世界をこのように秩序あらしめている本質的なものとしてロゴスを考えて、それロゴスこそ一切の中に遍在する真の本質であって、人間は自らロゴスの種を保有しているのであります、従って人間はその内在のロゴスを見証し、また開発するところに解脱があるのだと観ておったのであります。
ところがこれに対しパウロの抱いていた創造の唯一神観は全く対蹠的な立場にあったのでありまして、彼は造られたる世界と創造者である神とを、次元の異っている混同するべからざる関係として考えたのであります。
パウロにおいては、世界は神ではなかったのであります。神と世界との間には本質的に区別されるべき境界線が存在するとされたのでありまして、つまり世界事象はパウロにとってはむしろ歴史だったのであります。超越者である神の聖意の働きかけ給うところに世界は存在するのであります。
別言しますと、パウロの神は、「耐忍びて善をおこなひ光栄と尊貴(とうとき)と朽ちざる事とを求むる者には永遠(とこしえ)の生命をもて報い、徒党により真理に従はずして不義にしたがふ者には怒りと憤恚(いきどおり)とをもて報い給はん」(ロマ書第26日章)神だったのであります。
パウロが、このような創造神――正義神の見方と併行して強調するのが人間罪悪観であります。そしてこれがキリスト教の根本に横たわる一つの大きな難問となっていることは前に叙述した通りであります。
四、キリスト教とパウロ 自観叢書第7篇『基仏と観音教』