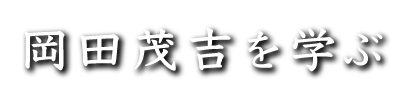一、パウロとユダヤ教
歴史上にパウロほど興味深く、また感激的な人間は実に稀である。
パウロはピリピ書の中で自分の生れた人種について誇らしげに書いておる。
「我は八日めに割礼を受けたる者にして、イスラエルの血統、ベニヤミンの族、ヘブル人より出でたるヘブル人なり」
と。パウロがこのように自分の血統のことを自画自讃するわけには、二重の意味があると思われる。つまり一つは、パウロがキリスト教の使徒、「イエスの奴隷」になる前に持っていた意味と、他の一つはパウロが使徒になってから後に生じてきた意味とである。
そして更に一歩進めて考えると、この二つの意味がお互いに混り合ってそこに面白い複雑な意味の世界を展開しているのである。ともかくパウロはキリスト教の原始時代に最も重要な地位を占めていた伝道者だったのである。小アジアのキリキア州タルソに生れた純粋のユダヤ人なのである。
パウロは初めサウロと呼ばれておったが、それはベニヤミン族に起った最初のユダヤ王サウルの名にあやかったわけであろうとされている。そして使徒行伝においてはパウロはこんなことを言って自分を振返っておるのである。(行伝二十二章三節)つまり、
「我はユダヤ人にてキリキヤのタルソに生れしが、この都にて育てられ、ガマリエルの足下にて先祖たちの律法の厳しき方に遵ひて教へられ、今日の汝らのごとく神に対して熱心なる者なりき」
というわけであった。まず第一にパウロを作ったものは、ユダヤ的伝統であり、ユダヤ的精神だったのである。パウロはパリサイ主義の家庭に生れ、そしてパリサイ主義の教育によって仕込まれ、パウロ自ら言っているように、
「又わが国人のうち、我と同じ年輩なる多くの者にも勝りてユダヤ教に進み、わが先祖たちの言伝に対してはなはだ熱心なりき」〔ガラテヤ書第一章〕
だったのである。パリサイ人としての厳格な教育を受けたユダヤ教徒であったわけである。
ではパウロがそれ程真剣に身を打込んでいたユダヤ教と言い、またパリサイ人と言い、一体それらはどんな関係でパウロを包んでいたのでしょうか、パウロとユダヤ教との関係が深ければ深いだけ「パウロの回心」と呼ばれているあの有名な心霊的体験の意味も深くなるのである。
さて、古代イスラエルにおいて、ユダ王がバビロニアの圧迫を受けて、政治的に没落してしまい又首都のエルサレムは西暦紀元前五九七年と五八七年の二回にわたって破壊されたのであり、そのとき国民の主なる者が捕えられ、囚人としてバビロニアに拉致されてゆき、これが史上有名はバビロニア捕囚と呼ばれるようになったものである。この政治的な没落とバビロニア捕囚とによってイスラエルは首をなくした胴になったわけである。
ところが囚人として拉し去られた人達は比較的に自由を与えられており、また生活的にもさしたる危険に曝されておったわけではなかったのである。けれども、故郷と神殿とを失ってしまったことは彼らにとって堪え難い悲しみだったことであろう。そしてこのことは却って逆に民族的精神と終末観的な思想とを強く養う結果にもなっていったのである。更にこのことは、言い換えると、彼らがその民族固有のヤーヴェ神(エホバ神の本名)の信仰を失わなかったことを証明してもいるのである。
こんな経緯を経て西暦紀元前五三八年になってから、ペルシア王の力によって彼らはやっと囚人の地位から釈放されたのである。そして彼らは帰国した後に、まずエルサレムに神殿を再建し、それからその神殿の儀式、並びに司祭に関する詳細な規定(いわゆる祭司法典)を設けたのであった。また通常モーセ経典の名で呼ばれているものは、彼らが先祖の宗教精神に拠って法規を編纂し修正を加えて出来上ったものなのである。ここに至って失くした首がもう一度胴についたという観方も成立する。これらのことは皆西暦紀元前五世紀後半のことであって、ユズラ及びネヘミヤの二人の力にまつところが非常に大きかったのである。
ところでユダヤ教というのは、このようにして発生してきた律法的な神殿宗教のことなのである。ユダヤという名称は、ヤコブの子ユダの後裔の住地の名ユダヤから出ており、また後にはイスラエル人を一般にユダヤ人と呼んだのに基づいておるのである。
この宗教はヤーヴェ神の崇拝であるが、古代の予言者達の道徳的な信仰と異っており、全く祭式儀礼と戒律との宗教であった。従って祭司並びに律法の教師としてのラビとがその指導者であった。それからやや後には祭司を中心とする党派サドカイ人と、厳格なる律法の遵守を最高の義務として努力するパリサイ人の派とが勢力を占めたのである。従ってパウロが受けたパリサイ派の厳格な教育というのは、旧約の律法と習慣法とを特に厳格に守ることを目的としていたのである。
パリサイ派の人達というのはそのような目的を持った人達なのであって、彼らが自分達のことを一般の人民と区別されるようにするため自らこのように呼んだのである。パリサイのヘブライ語源は「分離者」という意味がある。政治的には排他的であり、宗教的にはその宗教の精神よりもむしろ外形的、形式的なところを強調したものである。サドカイ派と共にキリスト教徒の迫害を遂行したのであるが、サドカイ派が政治的、感情的であったに反して、純粋に宗教的立場から迫害の手を加えたのである。
敬虔なユダヤ人の家庭の常であったように、パウロも幼年時代から「イスラエルよ聴け我らの神エホバは惟一(ただひとり)のエホバなり云々……」(申命記六の四)という黄金律をもってイスラエルの神に対する忠誠を鍛錬せられていったに相違ないのである。法律も文学も歴史もその他のあらゆる学問は、ただエホバを畏れ敬うことを中心としてこそ、その存在理由を持っておったのであ、り、ユダヤ人には特に宗教教育と名付けられるような分割的な教育はなかった。総てが宗教教育であったということが出来るのである。
これを裏書し、またパウロ個人の人為を如実に示しているものとして「ロマ書七の九」の次の言葉があります。
「われかつて律法なくして生きたれど、誡命(いましめ)きたりし時に罪は生き、我は死にたり」
と、十三、四歳になると「律法の子」としての全体的な責任を負わされ、また律法を厳密に遵守しようとする努力は本格的なものとなるのである。パウロはその頃からエルサレムに赴いて律法の学を修め、そしてラビとしての準備にいそしんだのでもあろうか、彼は前掲の通り使徒行伝において当時を振返っておるのである。つまりガマリエルの足下に律法の解釈学や、教義学に心身をうちこんだらしいことが窺われるのである。
厳格なるパリサイとして清純に律法の一点一画をも満足させようとする精進は事実尋常一様のことではなかったであろう。けれども、
「わが国人のうち、我と同じ年輩なる多くの者にも勝りてユダヤ教に進み、わが先祖たちの言伝に対してはなはだ熱心なりき」(ガラテヤ書一の十四)であった。そのような青年パウロの真剣な心持は律法実行の努力となって現われてくるのは自然である。そして、
「律法によれる義につきては責むべき所なかりし者なり」(ピリピ書三の六)
と言うことの出来る程に、パウロはひたすらに忠実だったわけなのである。
パウロはただ律法の命ずる所をなす事においてのみ聖なる神の前に立てるのだということを深い自覚から認識していたことであろう。しかし律法の重要性と、律法における生活の内的矛盾とがロマ書第七章七節以下に重苦しく記述されている。このパウロの内的な苦しみは単なる命令の関係に基づいた道徳上、倫理上の苦悶ではないと思う。もっと差迫ったものだったのである。自分の全存在と神との関係を問題にした事柄だったと思う。この矛盾が行き詰るところは死であり、滅亡であるわけである。
「わが行ふことは我しらず、我が欲する所は之をなさず、反つて我が憎むところは之を為すなり」(ロマ書七の十五)
という血のにじむような告白は、ユダヤ教のパリサイ派的律法生活において、パウロのかくれた心の悶えと呻きがどんなものであったかをほぼ推量させてくれる。それは最も深い意味において道徳的宗教的な苦闘であったと言い得よう。ただ神の御前でだけ照し出されたのみであって、人の前には秘されていたパウロの当時の内心の消息であったと考えていいと思うのである。
ともあれ、このようにユダヤ教に対して敬虔であったパウロが、パリサイ派の人として生活した日から深刻な問題となっていたものが、実は厳格な遵守を要求する当の律法そのものの行詰りであったのである。そしてそこにパウロ自らがキリスト·イエスを信ずるようになってしまった深い誘因をもなしていたと考えられるのである。
律法はただ実行の一点に関係しているのである。ところが人間は「肉によりて弱くなれる」事のために律法を成就させようとしても成し能わぬのであるから、結局律法の実行は不可能と言わなければならない。「肉の念は神に遵(シタガ)ふ、それは神の律法に服はず、否したがふこと能はず、また肉にいるものは神を悦ばすこと能はざるなり」(ロマ書八の七、八節)
だからなのである。ところが信仰によって義とされた、生活は
「しかれど縛られたる所につきて我らいま死にて律法より解かれたれば、儀文の旧きによらず、霊の新しきに従ひて事ふることを得るなり」(ロマ書七の六)
となるわけであって、律法の支配より解放されて、恩恵によれる聖霊の支配下にたたされた生活となってくる。そしてそこに赦しが与えられているだけでなく、潔きに至る能力を得られたのである。だから十字架にかけられたキリスト·イエスなどというものは信じられなかったばかりではない。パウロは純粋のユダヤ人であることを、そしてまた律法に生きるパリサイ派の人間としての誇りを調べ高くキリスト教徒の迫害へと切り替えたのである。それは律法宗教の内的矛盾に心悩んだパウロのいたましい自虐だったとみるものすらあるのである。
二、パウロの神霊体験
パウロが程度の高い霊能力の所有者であったことは、彼がキリスト教徒迫害の信念を燃やしながらダマスコへ追跡の足を向けたその道すがらで突発的に示されたのである。
『往きてダマスコに近づきたるとき、忽ち天より光いでて、彼を環り照したれば、かれ地に倒れて「サウロ、サウロ、何ぞ我を迫害するか」といふ声をきく。彼いふ「主よ、なんぢは誰ぞ」答へたまふ「われは汝が迫害するイエスなり。起きて町に入れ、さらば汝なすべき事を告げらるべし」同行の人々、物言ふこと能はずして立ちたりしが、声は聞けども誰をも見ざりき。サウロ地より起きて目をあけたれど何も見えざれば、人その手をひきてダマスコに導きゆきしに、三日のあひだ見えず、また飲食せざりき』(使徒行伝九の三-九)
このような心霊現象は彼パウロにとって今迄にただの一度もなかったことなのである。ソクラテスのダイモニオンが彼の幼年時代から聞えていたのとはわけが異っていたのである。けだし、全体としてのパウロを理解する上には、この神霊体験によって惹起されるに至った彼の全人格的革命を一つの大きな転換点として考えるゆき方がとられねばならない。それ程にこの体験の意味は深かった。
パリサイ派の人としてのパウロも、それから「生まれながら」にしてローマ市民権を持っておりかつヘレニズム文化との接触の中にあるパウロも、つまるところこの神霊体験を経て、イエスの僕となり、キリストの使徒となったパウロに至るまでの単なる準備だったに過ぎなかったかのように、実はパウロ自身でも考えていたのである。
それから後の全生命を打ち込んでなし遂げ、そして殉教していった使徒としての職は、ただこのときに受取った使命への応答であり、パウロを占領して離さなかった驚くべき愛の精神の発露だったのである。もしもこの時機がパウロに体験されていなかったならば、世界史には「使徒パウロ」は見出すことができなかったであろうし、またキリスト教史は今日書かれているようには、よもや書かれはしなかったことであろう。
パウロのこの入神状態は言うまでもなく復活のイエスに捉えられた体験である。
そしてその後においてパウロを動かした本質的な能力は聖霊であった。そして彼自ら言っているように「聖霊の中に歩む」ことこそパウロの生活であったと言うべきであろう。古いものの崩壊と焼却によって新しい生命が産み出されるのである。死ぬことによって生きるということは、既に生命の内部にあってさえ、核心的なことなのである。
パリサイ派の人としてのパウロ、律法に生きたパウロは、この激しい神霊の体験によって完全に崩壊し、また焼却されて無に帰し、三日も失明した、そしてその中から復活のイエスに捉えられ、イエスの奴隷としての新しい生命に整ってきたのであろう。
そこからパウロの二重視覚が始まるのである。ヘブライ人であるという誇らしげな自覚もここから意味が二重になってくる。
「最早われ生くるにあらず、キリストわれ〔が内〕に在りて生くるなり」
というのは、パウロの最も深い霊的体験を述べた言葉であろう。パウロは自分のたてた伝道方針も「霊のみちびき」によって全然変更してしまうことさえあった。またパウロはしばしば「幻」をも見た。彼の生涯における転機は、このような神秘的経験によって決定されていることを見る。ガラテヤ書第二章二節には、パウロのエルサレム上京は「黙示に因りて」であったことが力説されている。
また異言を誇るコリント人に対しては、「我なんぢら衆(すべて)の者よりも多く異言を語ることを神に感謝す」(コリント前普第一四章一八節)
と述べている。パウロはまた、一般に忘我的恍惚境と言われている状態に陥るようなこともあったとされている。それがいわゆる入神状態である。パウロはコリント後書で、
「第三の天、パラダイスに取り去られて(肉体にてか、肉体の外にてか、われ知らず)言い得ざる言、人の語るまじき言を聞けり」
としるしている。一方実際的な宗教政治家であり、また常識的な教会指導者であったパウロは、同時に夢幻に導びかれたと普通考えられているように、霊視能力の所有者であったし、また忘我的心境裡と一般に呼ばれているいわゆる入神状態において、天来の声に耳傾けた神秘家でもあったのである。
それは言い換えれば霊聴能力の所有者であったのである。そしてパウロの守護霊団には「世の霊にあらず、神より出づる霊」(コリント前書)があったことが判るのである。では一体「神の霊」それ自身はいかなる意義をもっているのであろうか。パウロはこの事を理論的に説明していない。ただコリント前書の二の十、及び十一において断片的に触れているに過ぎない。
「しかれど我らには神これを御霊によりて顕し給へり。御霊はすべての事を究め、神の深き所まで究むればなり。それ人のことは己が中にある霊のほかに誰か知る人あらん、かくの、ことく神のことは神の御霊のほかに知る者なし」
非常に断片的だけれども、これらの言葉は御霊が神から離れた実体でもなく、神に所属する奉仕者でもないことが窺われる。それは神の本質の裡にあるのであって、人が御霊にあずかるとき、それは神の本質の中に捉えられるのである。だからパウロにとっては御霊に「あずかる」とか、御霊に「みたされる」とか言うことは、ただ宗教的な、また倫理的な能力にみたされる事でもなければ、社会的精神によって占領されるというような事でもない。それは実に超自然的な神自らの本質に結合され、神自らのものとなる事を意味している。
このような意味でも法悦境、恍惚境に遊んだパウロの体験は、彼のダマスコ途上の入神状態以来しばしばあったと伝えられている。けれどもそのような体験の内幕はパウロ自身が語ってくれなければ他人には全然判るものではない。幸いエペソ書第一の十三、及び十四にはそれを窺わしめてくれるものがある。
「汝らもキリストに在りて真の言、すなはち汝らの救の福音をきき、彼を信じて約束の聖霊にて印せられたり。これは我らが受くべき嗣業の保証にして、神に属けるものの贖はれ、かつ神の栄光に誉あらん為なり」
とある。こうなってくると、結果は世界の終末という考え方と関係をもたせて考えてみないとこのパウロの入神状態の本当の意味はよく理解されるようにはならないかもしれない。
ともかく、パウロはその魂の一つの大きな体験を経て、キリストの福音とその救いとを信じ、これよりキリストの福音の伝道者として、その使命を自覚したわけである。しかもその福音はユダヤ的な律法を条件としなかったから、民族的な、また社会的な差別なしに全ての人に伝えられなければならないという確信を抱いていた。そこで自分から進んで異邦人に対するキリストの福音の伝道者となったのである。しかしパウロのこの異邦人伝道の目覚しい成功は言うまでもなく、彼の信仰と神霊体験からきた熱情によるところが極めて大きかった。けれどももう一つ、それらに加えて、一面「聖霊の中を歩いた」彼の政治的才能にあずかる所も少くなかったことをも認めなければならない。彼には計画があったのである。ただ単に熱情にまかせて盲動したのではなかった。
ロマ書第十五章二十節によれば、パウロはまず、
「努めて他人の据ゑたる基礎(もとい)のうへに建てじとて未だキリストの御名の称へられぬ所にのみ福音を宣伝へ」
たのであった。つまりパウロは開拓的伝道を彼の方針とした。それから彼は都会中心の伝道を遂行した。これは恐らく、主の再臨までに、なるべく多くの人達にイエスの御名を伝えようとの意図に出たものであろう。
一つの都市に入れば、彼はまずユダヤ人会堂を利用した。これは同胞の救を全うしようとする願いをもったためと、また会堂に出入する「神を畏るる」異邦人に近づかんがためであった。このようにして若干の信徒が出来れば、パウロは「長老たちを選んで」教会の指導に当らせたのである。またパウロは地方における諸教会とエルサレムにおける母教会との連絡を保つことに努めもした。
パウロがエルサレムにおける「貧しき聖徒」のための募金運動で奔走したのは一面においてこのような教会の統一を計るためでもあった。これらの点において、パウロは実に卓絶せる教会政治家であった。しかしパウロは自分一人で全てをなそうとはしなかった。常に多くの同労者、戦友を伴い、あるいは指揮した。
そして更に「聖霊」からの通信のまにまに、「聖霊」と共に働いたわけである。
「もし我ら御霊に由りて生きなば、御霊に由りて歩むべし」(ガラテヤ書第五の二十五)
聖霊の中に歩む生活とはキリストにありて生くる生活である。
「もしイエスを死人の中より甦へらせ給ひし者の御霊なんぢらの中に宿り給はば、キリスト·イエスを死人の中より甦へらせ給ひし者は、汝らの中に宿りたまふ御霊によりて汝らの死ぬべき体をも活し給はん」(ロマ書第八の十一)
このような自覚に基づくパウロの活動はエルサレム教会のある人々との衝突を招いたが、彼はその頭首であったペテロ等と妥協して、結局小アジア、マケドニア、ギリシア等異邦人の世界への伝道に専ら努力したのである。
ところがパウロに対する反感はユダヤ人中に次第に強くなり、その煽動によって人民の騒乱が起った。そしてその結果彼は捕えられたが、自分からローマへ送られるように訴え、ローマ王帝ネロの頃殺されたといわれている。ネロがパウロを殺した罪状の中には、恐らく彼の心霊能力が悪魔と交通し、それと結托して人心を欺くもの、などといったようなことが加えられていたことであろう。
要するに、パウロは偉大な霊能者であり、霊覚者であったと考えていいのである。