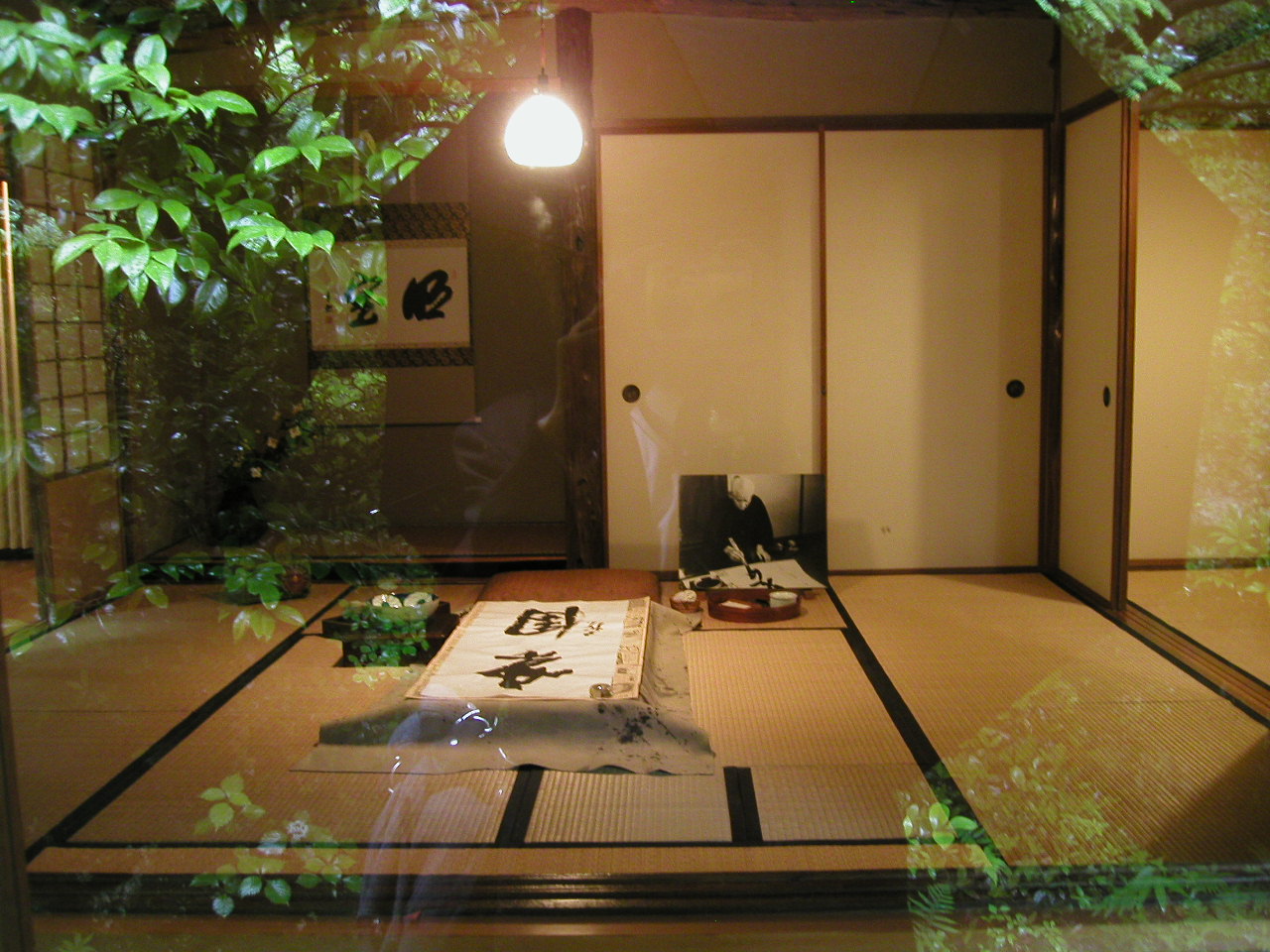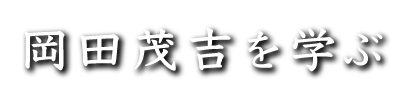《お伺い》フェノロサと一緒に来たピゲロと云う者が、肉筆の物許りを買って帰り、亡くなって子供が外国で売ろうとしましたが、売れず。日本で売れる様になり、その目録が私の方に参っておりますが――よろしければ御献上させて戴きたく思っております。
《御垂示》フェノロサ時代でしょう。あの時代には、古い良い物は手に入らないですよ。良い物はみんな大名、財閥でね。
《お伺い》浮世絵の肉筆は売れないとの事で。
《御垂示》その時代に、売物として出た物は良い物じゃないですよ。と言うのは、私が知らずに随分買ったんですよ。品物が気に入ってね。それが後で調べてみると、画家の代表的な物ですよ。で、日本一と言うのがありますよ。団琢磨と言う人が持っていたのでね。「湯女」と言ってね――之は日本一です。日本で一番良いのは「湯女」と「彦根屏風」――この二つです。「彦根屏風」は、屏風ですからね。戦争で疎開する時離したんです。今度やると、新規に仕立て直さなければならない。屏風だと一段落ちますからね。そうすると、「湯女」ですが、之は博物館で非常に狙っている。
肉筆に贋物と言うのは、滅多にないですよ。処が、版画でも、初版とその次がありますからね。
《お伺い》外人は鑑識眼が勝っているので御座いましょうか。
《御垂示》研究しているからね。大抵浮世絵と言うと、桃山期以後ですよ。幕末迄が良いんです。私が一番好きなのは、桃山ですね。 兵児帯しめているのですね。
《お伺い》初期の物で、墨絵の。
《御垂示》初期なら春信ですよ。古いのは、筆者を入れないものですよ。私は、版画は趣味がない。版画が良いと言うのは、画家と印刷職工の、その腕を褒める様なものだ。版画では、絵は死んでますよ。古い良い物は、落款が無いですよ。落款は入れなかった。浮世絵でも仏画でも、良い物は落款が無いのが多い――古いのは姿が特に良いんですね。懐月堂も好きですがね。ありますがね。あれは少し、下手物染みている。品格が薄い。やっぱり、良い物は春信、春章それから光起。
《お伺い》清長が境で。
《御垂示》清長でも、私なんか、一寸面白くない。それから、師宣が良いです。光起ね。品格がありますよ。又兵衛ね。その中で、又兵衛が一番ですよ。それは無いが、一寸高いですよ。
《お伺い》日本芸術の高さを、外人が鑑賞出来ると言うのは、そう言う特種な才能を持った人が解るので御座いましょうか。
《御垂示》それじゃいけない。才能も何もない。誰が見ても良い。目が利いてる人が見て良いって言うのは、本当ではない。誰が見ても良いもの――そう言うのが本当の芸術です………一人でも多くの人が楽しむって言うのが本当です。目が利いていても、いなくても、本当に良いと言うのが芸術です。今度、私はそう言うのを出そうと思っている。一人が喜ぶと言うのは、芸術ではないんです。
《お伺い》今迄、アメリカでは喜び、日本では左程でなかったと言う事は生活の為に向かれなかったので御座いましょうか。
《御垂示》封建主義の為にされなかった。大名、富豪――みんな特権階級ですよ。然し、大変な功績を残してますね。大名が集めて、支那芸術が残されているので、大変良かったです。それから財閥ですね。財閥と言うと、明治以後ですがね。大体、大阪ですが、淀屋辰五郎と鴻池ですね。淀屋はつぶれてますが、鴻池は残ってます。数から――良い物から行けば、一番ですよ。大名でも色々ありますが、何と言っても松平不昧公です。大したものです。不昧公は茶器ですがね。茶器の良い物は、不昧公の手に一度渡ったものですね。面白い話ですが、大徳寺にある――喜左衛門井戸は、不昧公が持っていた。処があれを持っていて、暫くしてからオデきが出来て死んだんです。その息子がそれを愛玩してたが、親父と同じで死んだんです。それで、之はお寺に寄付するよりないと、大徳寺に寄付した。そう言う不気味な伝来がある。偶然にそうなったんでしょうがね。明治になってから、色んな財閥が集めましたがね。で、大名の中でも、相当集めたのがありますがね。酒井家ですね。二軒ありますがね。酒井忠信さんに酒井何とか――ここは、祖先が相当集めたんですね。それから蒔絵物は加賀ですね。前田家ですね。明治になってから――明治以後民間に散らばったですね。
《お伺い》藤田組などは、全部進駐軍に抑えられましたが、あとはいかになっておりますので。
《御垂示》皆んな売ったですよ。進駐軍に抑えられても、出してます。もう解けただろう。
《お伺い》今度は、財産税の事で、売る訳には。
《御垂示》けれどもね。何か手段がありますよ。
《お伺い》蒔絵類は、他の美術品に較べて、安いのでは。
《御垂示》安いですよ。
《お伺い》外国では保存が出来ません様で御座いますが。
《御垂示》そうじゃない。良い物でなく、悪い物だからですね。アメリカは乾燥していて、空気が悪いからですよ。日本人は、こすいと言うか、利口と言うか、良い物はやってないですね。日本美術なんて言うのは、みんな贋物ですよ。先に浜蒔絵と言って、横浜で、金でピカピカしたのを作ったものです。ああ言うのを、みんな向うに売込んだんですね。それで、本当の物は行ってないんです。それで、本当に拵えた物は、あっちに行ったって大丈夫なんです。蒔絵は、乾燥がいけないんで、みんな割れちゃう。剥がれちゃうんです。ドイツで、日本の漆器を真似して――実用品ですが、随分出しました。ウルシを使わないで、他の塗料でね。蒔絵は良い物が出来てます。船が――博覧会の出品物が積んであったのが沈んで、二ヵ年沈んでいたのを、引き上げて――先に博物館によく出てましたが――何ともない。塩水だから、銀の様なのは、錆びてますが、蒔絵は何ともない。二年漬かっていたんです。それは、昔の布切れと言って、布で、ウルシですっかり作り――何ともない。出来あがると、同じですからね。今でも天平時代の蒔絵がありますからね。経箱なんかね、千二百年位経っているでしょう。それが、ちゃんとありますからね。藤原時代なんか――八百年経ってますが、ちゃんとしたのがありますよ。作り方ですよ。陶器なんかは、そうではないですがね。欠ける丈ですからね。支那のなんか、殆んど欠けてます。と言うのは、発掘物だから、掘出す時に欠いちゃう。支那、朝鮮の陶器の良い物で、疵の無いと言うものは滅多にないですね。その代わり、疵が無いと大変ですよ。
《お伺い》陶器類が一番難しい様で御座いますが。
《御垂示》難しいと言う事はないが、支那の青磁ですね。他にそうないですね。青磁で、日本で本当に青磁の分かる人はないでしょう。
《お伺い》清朝のもので。
《御垂示》乾隆ですね。
《お伺い》清朝に伝わっているもので、それに対する贋物を作ったと言う事で御座います。
《御垂示》清朝に真似するとすれば、明時代の物ですよ。宋時代の物は絶対に真似出来ないんです。不思議なものですよ。
《お伺い》白地に色々な色を使った、綺麗なもので。
《御垂示》綺麗ですが、明時代ですよ。明時代の清朝ものは丸っきりです。宣徳、嘉靖、万暦――この三つの時代がですね。赤い物ですよ。処が宋時代には赤絵は少ししかない。大抵無地物です。私は無地物が好きで相当集めたが、そのうちで青磁が一番好きです。青磁も色んな学者の意見が、人によって異うんです。古い新しいは分かりますがね。支那は窯が沢山ありますからね。之は何処の何の窯で焼いたと、学問的になって来る。処が支那の窯と言うのは、1000以上あるんです。それで各時代の王様が、自慢で良い物を作らせた。その時代の名人にやらせたんですからね。そうして良い物を取って、気に入らないのは、みんな壊した。だから、支那の陶器の窯のある所に行くと土を掘ると幾らでも出て来るんです。日本人なんかが研究に行って掘るんですよ。其処から掘出して、之は、品物を合わせてみて、之は何の窯で出来た、となるから、意見が皆んな異う。だからアメリカだってイギリスだって、陶器は支那陶器ですよ。その中で、私が一番好きなのは宋均窯ですが、あれが一番好きです。
私は、一番不思議に思ったのは、去年広重の版画ですが、五十三次で――よくありますが――広重の絵を持って来た。私は、五十三次すっかり揃っているのがあったら――初版ですよ――買ってやると言った。それで帰って、翌る日か持って来たんですが、紀州公が持っていたんで、紀州家の文字が乗ってあるんです。そう言う素晴らしい物を――二巻ですかね。初版で綺麗なんです。大名が持っていたんですからね。綺麗なんです。それが、私の話を聞いて帰ったら、その日に持って来たと言うんですからね。それで、自分は広重の初版を欲しいと思っていたが、四十年来入らない。処が、お話を聞いて帰ったら、その日に来た。どう考えても不思議だと言うんです。
《お伺い》普通の物で、二十年位前で五、六千位で御座いました様で。
《御垂示》橋口五葉と言うのは、私は好きです。あれは良いですね。――六、七枚あるかね。種類はあんまりありませんね。確かに価値があるね。