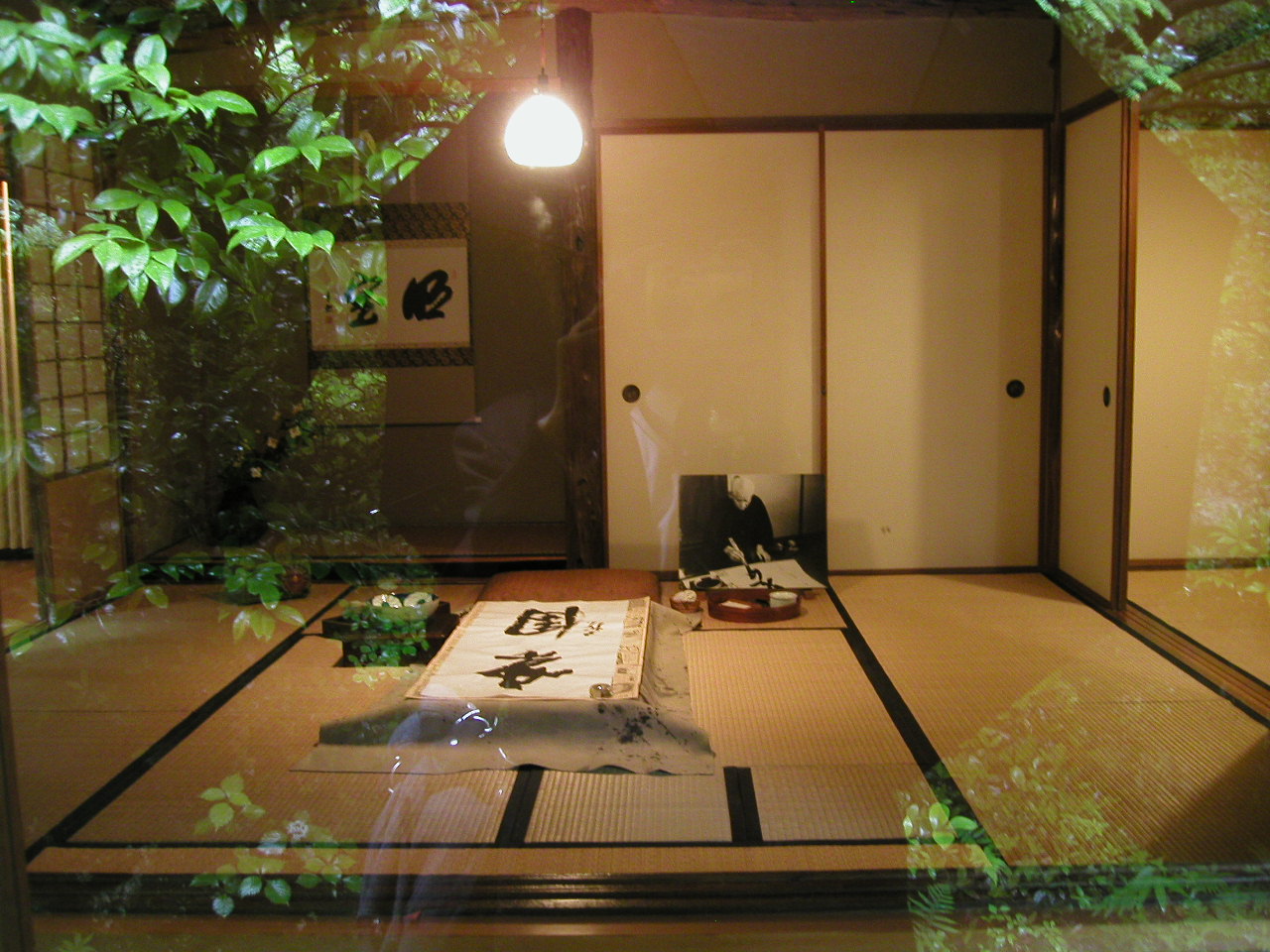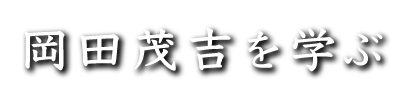前項迄に、観世音に就(つい)ての因縁を、色々な面から説いて来たが、そうなられる迄の根本と言えば全く素尊の暴圧が原因であった事は、既に述べた通りである。処が伊都能売(いづのめ)神去り給いし後の日本は、どうなったかというと、其(その)弟神であったのが、彼の天照天皇であって、此(この)天皇は惜しくも、何の理由もなく俄(にわ)かに崩御(ほうぎょ)され給うたので、止むなく其皇后を立てて、御位(みくらい)に即(つ)かせられたのが彼の女性である天照天皇であった。今も尚天照大御神が日の神であり乍(なが)ら女神として祀られているのは、そういう訳なのである。又以前私はかいた事があるが、素尊は日本の統治権を得んとして余りに焦り、目的の為に手段を択(えら)ばず式で、力の政治を行った結果、人心は紊(みだ)れ、収拾すべからざるに至ったので、茲に父君である伊邪那岐(いざなぎ)尊の御勘気(かんき)に触れ、譴責(けんせき)の止むなき事になった。というのは素尊は、本来朝鮮系統の神でもあったからである。而(しか)も其後悔悟の情なく、依然たる有様なので、最後の手段として日本を追放される事になったのである。此時の事を古事記には斯(こ)う出ている。素盞鳴(すさのお)尊の素行や悪政に対し、伊邪那岐尊の御尤(とが)めを蒙(こうむ)り、神遺にやらわれたとあり、其行先は黄泉(よみ)の国であるが、黄泉の国には母神である伊邪那美(いざなみ)尊が在すので、罪の赦(ゆる)される迄母神の許にいて、暫くの間謹慎すべく思って、出発の前、天に在す姉神天照大御神に暇乞(いとまご)いをせんとしたのである。此事を古事記には斯うかいてある。素盞鳴尊は忽(たちま)ち山川響動(どよも)し、天に昇らんとした処、それを知った天照大神は大いに驚き、さては弟素尊は、自分を攻めに来たのではないかと疑心暗鬼を抱いていた処へ、素尊は天に上り、天照大神に面会された処、どうも姉神の様子が普通でないので、之を見てとった素尊は、姉神は私を疑われているようであるが、自分の肚は何等の邪念はない。此通り潔白であるから、今其證(あか)しを御眼にかけると言い、素尊は剣を抜き天の真奈井の水に注ぐや、忽(たちま)ち三女神が生れた。即ち市杆島姫(いちきしまひめ)命、湍津姫(たぎつひめ)命、田露姫(たぎりひめ)命である。すると天照大神は、では自分の清い心も見せようと申され、胸に掛けた曲玉(まがたま)を外(はず)し、同じく水に注ぎ揺らがした処五男神が生れた。即ち天忍穂耳(あめのおしほみみ)尊、天穂日(あめのほひ)命、天津彦根(あまつひこね)命、活津彦根(いくつひこね)命、熊野樟日(くまぬくすび)命である。勿論之は比喩であって、実際は其時、素尊は三人の息女、天照大神は五人の重臣を呼んだのである。というのは此時両神は、右の五男三女を證人として、一つの誓約(うけい)をされようとしたからで、其誓約とは近江の琵琶湖一名志賀ノ湖、又右の天の真奈井もそうであって、此湖水を中心として、東の方を天照大神、西の方を素盞鳴尊が領(うしは)ぐという約束をしたのである。つまり今日で言う平和条約である。之によって兎(と)も角一時小康を得たが、其後素尊は相変らず謹慎の色が見えないので、茲に本当の追放となったのである。此時の事を八洲河原の誓約(うけい)と言われているが、今日でも琵琶湖の東岸に八洲河原という村があるのは、此地点であったのであろう。
茲で昔から、人口に膾炙(かいしゃ)されている龍宮の乙姫という女神の事をかかねばならないが、之に就ては、少し遡(さかのぼ)ってかく必要がある。それは伊邪那岐、伊邪那美尊から生れた五柱の男女の兄弟がある。即ち長男は伊都能売天皇、次男が天照天皇、三男が神素盞鳴尊、長女が稚姫君(わかひめぎみ)命、二女が初稚姫(はつわかひめ)命である。そこで伊邪邦岐命は、最初伊都能売尊に日本を統治させ次で天照天皇次で天照皇后の順序にされたのであるが、素盞鳴尊には最初から朝鮮を統治させたのである。そうして素尊の妻神とされたのが、勿論朝鮮で出生された姫神であって、此姫神が弟の妻神となった、言わば弟姫であるから、之を詰めて音(乙)姫と呼ばれたのであるが、昔から乙米姫とも言われたが、之は未婚の時に朝鮮名の中に、米の字が入っていたからであろう。
右の如く、弟姫即ち音姫は、夫神が流浪の旅に上られたので、それからは孤独の生活となったのは勿論で、間もなく故郷の朝鮮へ帰り、壮麗な城廓を築き、宮殿内に多くの侍女を侍らせ、空閨(くうけい)を守っていたのである。処が其頃信州地方の生れである太郎なる若者が、漁が好きなので、常に北陸辺りの海岸から海へ出ていた。すると或(ある)時大暴海に遭い、辛(かろう)じて朝鮮海岸に漂着して救われたが、当時としては日本人も珍しがられていた事とて、遂に男禁制の王城内に迄招ぜらるるに至ったのも無理はない。処が当時女王格である音姫様は、寂寥(せきりょう)に堪えなかったからでもあろうが、兎(と)に角御目通りを許された処、太郎という若者が、世にも稀なる美貌の持主であったから堪らない。一目見るより恋慕の情堪えやらず、遂に何かの名目で、城内に滞在させる事となった。
其様な訳で、太郎に対する愛情は益々熱烈を加え、日夜離さず御傍に待(はべ)らせるという訳で、此事がいつか人民の耳に入り、漸(ようや)く非難の声喧(やかま)しくなったので、茲に絶ち難き愛着を絶つ事となり、素噴らしい宝物を箱に納め、土産物として太郎に遣(や)り帰国さした。之が彼の有名な玉手箱である。又之を開けると白髪になるなどという伝説は、誰かの作り事であろうし、又浦島という姓は、朝鮮は日本の裏になっているからで、後世の作者がそういう姓を付けたのであろう。
そうして音姫が朝鮮の女王格であった時代は、日本も支那も圧倒されて了い、印度以東は朝鮮の勢力範囲といってもいい位であった。勿論それは素盞鳴尊が、一時飛ぶ鳥も落す程の勢いであったからでもあり、其上音姫という女神は男勝りの女傑であったからでもある。恰度(ちょうど)其頃印度の経綸を終えた観自在菩薩は、帰国しようとして南支方面に迄来た処、まだ日本は危険の空気を孕(はら)んでいる事が分ったので、暫く其地に滞在する事となったので、其時からが観世音の御名となったのである。という訳はつまり印度滞在中は、自在天の世を客観していたので観自在といい、今度は音姫の世を静観する事となったので、観世音と名付けられたのである。即ち観世音を逆に読めば、音姫の世を観るという意味になる。そうしておいて菩薩は、南支那(しな)地方民に教を垂れ給うた処、何しろ徳高き菩薩の事とて、四隣の民草は親を慕うが如く追々寄り集う有様で、此時から観音信仰は遂に支那全土にまで行き渡ったのである。処が御年も重ね給い、之迄で経綸も略々(ほぼ)成し遂げられた事とて、遂に此土地で終焉(しゅうえん)され給うたのである。そうして今日と雖(いえど)も支那全土即ち満洲、蒙古、西蔵(チベット)辺りに到る迄観音信仰のみは、依然として衰えを見せないのは深い理由のある事であって、之も追々説くが、茲で遺憾な事は、南支地方に観音の遺跡がありそうなものだが、全然無いのは、全く其地方が幾度となく、兵火に見舞われ、地上にある凡(あら)ゆるものが消滅した結果で亦止むを得ないのである。