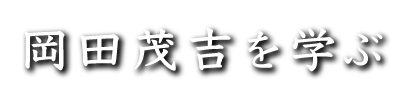中毒症のものは必ず治るものです
《お伺い》六年前にメチールで盲になった者の御浄霊の急所はどこでございましょうか。
《御垂示》目をやれば良い。メチールで、最初に目が見えなくなるが、うっちゃらかしておけば良いのです。メチールの毒が目の上に固まっているので、うっちゃらかしておけば溶けて出てしまうのが、目薬をさしたりするので固まってしまうのです。目の後ろと目をやればきっと治ります。だからああいった中毒症のものは必ず治るものです。死んではしようがないが、生命のあるものは必ず治るものです。それを医者に行って目薬をさしたら駄目です。
黄疸の時の薬毒
《お伺い》以前黄疸を致し、色んな薬を相当に飲んでおりますが、冷たい水に入ったり洗濯の場合に手足が腫れますが、薬毒でございましょうか。
《御垂示》薬毒です。何かの薬です。黄疸は色んな薬を飲むから、やっぱりいずれかの薬毒です。全く医学というものはしようがないものです。
冷いとそこに毒血が集まり、それから火傷すると集まるという毒もある
《お伺い》疥癬になります前に、冬、顔を洗おうとして冷たい水に手を入れますと、その刺激で二、三時間感覚が無くなりました。それよりしばらくして疥癬の御浄化を戴きましたが、やはり毒の。
《御垂示》そうです。それで薬の性質によって、冷いとそこに毒血が集まり、それから火傷すると集まるという毒もある。火傷をするとよく膿をもつが、火傷をするとその刺激によって集まるのです。やっぱりお灸と同じです。冷たいのはその反対の性能を持った薬です。
サ行の発音が出ない幼児
《お伺い》九歳の男、頭脳は普通で薬毒もなく病気もしておりませんが、サ行の発音が出ません。どういう関係でございましょうか。
《御垂示》よくあります。舌の関係です。ここ(頸部淋巴腺)のどこかに固まりがあります。サ行に動かないのです。
元の仏教に戻りたい
《お伺い》明治時代に仏教より神社神道に変わっておりましたのが、元の仏教に戻りたいというのが三人ございますが。
《御垂示》信仰した訳ではないでしょう。それでは仏教で良いです。
《お伺い》全部。
《御垂示》全部良いです。
《お伺い》信仰して変わっており。
《御垂示》しかし、それは信仰ではありません。信仰した訳ではありません。根本的に神道になった訳ではない。規則だったのですから。
仏壇に水
《お伺い》仏壇に毎朝お茶を上げますが、それ以外にお水を上げます事はいかがでございましょうか。
《御垂示》それは新仏には上げるのです。一年間位は水を上げた方が良い。
《お伺い》その場合朝だけでよろしいので。
《御垂示》良いです。
一寸八分の木像の観音様
《お伺い》戦国時代の一寸八分の木像の観音様を支部長が買い受けましたが、先祖代々伝っているものだそうでございますが、御開眼お願い戴けますでしょうか。
《御垂示》良いです。それは、護持仏といって戦に行く時に腕に御守りとして縛って行くので。そうして戦に行くのです。ですから、一寸八分の金のが多いです。木のは少ないです。木の方が軽いといった意味でしょう。そうして頼朝時代に非常に流行ったのです。つまり護持仏と言って、持って歩くという訳です。それもその一種です。金箔は塗ってありますか。
《お伺い》塗ってありません。
《御垂示》木彫ですか。よほど古いですか。
《お伺い》代々伝わっているそうでございます。
《御垂示》古ければそうです。新しいのなら、ただ拝む為に一寸八分のものを作るという事はよくあります。今でもあります。
《お伺い》戦国時代にはそういうのを用いたのでございましょうか。
《御垂示》沢山あります。
《お伺い》御守護を戴く為でございましょうか。
《御垂示》そうです。良いのは純金なんかが入ってます。浅草の観音様はそれが御神体だったのです。浅草の観音様というのは頼朝が作ったのですから。最初は頼朝の護持仏だろうと思います。それが明治になってから無くなったが、売ったのです。それはいつか話したが、私の曾祖父が質屋をしていた。そこに質に入れた。浅草の長昌寺という――始終遊びに行った寺です。一年に一回御開帳と言って、観音様のお供をして行き、すむと長昌寺に帰って来る。ところが長昌寺の坊主が道楽して金を使って、私の曾祖父のところに質に入れたのです。で、私のところに暫くあったのです。ところが私の曾祖父は子供が無かったので養子をしたが、極くお人好で財産をつぶされて、その時に離した。一寸八分の観音様というのは沢山あるのです。あれが仙台にあるとかよく話がありましたが、みんなその時代の大将の使った護持仏です。純金ですが、段々位が下になると十六金、十四金、極く下になると六金というのがある。六金というのは銅が多いから錆びて黒くなっている。磨いているとピカピカ光って来ますが、銅みたいな光です。
《お伺い》今も浅草にはございますのでしょうか。
《御垂示》あります。今あるのは木彫に金箔を塗ったのです。木彫の一尺位のは方々のお寺の御神体になってます。観音寺の御神体もそうです。白布に巻いて御厨子に入れて、一年に一回管長でなければ開けてはならない。それを普通の人が見たら目がつぶれるとか言ってます。誰も見た人はないでしょう。私は神様のお知らせで分かったのです。