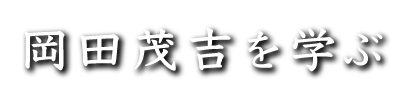昭和24(1949)年10月25日発行 観音教団編纂部
釈迦は中央インドは今のウード地域にあったカピラ城の太子として生れました。青年期に達した時、それまでに醸成されて来ていた太子の無常観は日一日と強くなり、そして厭世出家の時期は次第に準備されていたのでありました。つまり誰も避けようとして避けられない生老病死というような人間の現実に触れるにつけ、また太子の眼に映ずる光景はどれ一つとしてその心情を動かさないものはありませんでした。太子が断然出家して深く学理を究めて、生老病死というような人生の苦痛を免れるべき方法を知ろうとし、新宗教創設の道程に太子を上らせた動機は「無常」の観念であったと申せましょう。
深く人生を観てみますと、人間の生命は長いと思えば長いし、短いと思えば短いのであります。一度経験してしまったことは同じものが再びやって来ません。今日はすでに昨日ではなく、明日もまた今日ではありません。一切の事は一瞬毎に過ぎ去って永遠に帰ってはこない。そして未来は一瞬毎に現在の中へ飛びこんで来るにはくるが、現在はただ刹那刹那の転変でありまして、一瞬たりとも止らないのであります。まことに逝く水のような、また飛ぶ矢のような、一生涯はちょうど電光石火と何ら異っておりません。このように人生は全く無常であります。一生は本当に夢のようでありまして、生命の両端は直下に二つの不思議な世界に接続しており、死後と生前とは空々漠々としていてはっきり知ることができません。
ここに想いをこらしてみると、人は一層深遠な考察によって安心立命を求めるようになりますが、それは極めて自然なことと申さねばなりません。このようにして、釈迦は遂に出家を企てました。そして金殿玉楼をも弊履(へいり)のように捨ててしまい、乞食の姿となって真の解脱は果してどこにあるのかを求めようとしたのであります。釈迦はこの時二十九歳でした。妻子を捨て、王位を捨て、また王城を去って、解脱の道を求めたのであります。こうして林中での六年間の苦業の後に、あの有名な菩堤樹の下において彼が三十五歳のとき、人生苦痛の本源を看破して、根底より解脱し、生死の外に出られたのであります。
つまり十二因縁法なるものを観法し、また無明や煩悩を滅したのであります。ここにおいて釈迦は八面冷瓏となったわけであります、すると森羅万象皆ことごとくその真相を呈して映写して来たのであります。これを釈迦の「成道」と申します。この時から釈迦は、「一切成立せるものは無常なり、ただただ精励して解脱を求めよ」という最後の言葉を残して入滅するに至るまでの期間、一般衆生の安心立命と解脱救済とのために全てを捧げたのであったのであります。
仏教というのは、釈迦がそれを唱道し始めた当時の古代インドにおいては一つの新興宗教の名称であったわけで、そのことをここに詳しく論ずる必要はありません。
釈迦が生れました古代インドには当時四つの社会的な階級がありました。第一が僧侶階級、第二が王族階級、第三が農商階級で、第四が奴隷階級でありました。もともとインド人は、信仰心が非常に強烈で、神々を尊信するのは勿論のこと、この僧侶達を神々と人類の媒介者であるとしてほとんど神々と同一視するほどの傾向にあったのであります。この地盤と背景とを利用して僧侶階級は次第に権能を増大し、遂に極端に驕慢(きょうまん)となっていました。そして釈迦が王族階級に長子として生れてきた頃には既に恐るべき勢力を持っていたのであります。従って宗教上の事は一切この僧侶階級が統轄していたのは言うまでもありません。そしてその経文であるヴェーダは最高の聖典とされておったのであります。
ところが釈迦が現われるに及んで、身は王族階級に属していながら、自ら新しい宗教を唱道して、遂にヴェーダの聖典を否定するようになったのであります。この釈迦は西暦紀元前六世紀の中頃から五世紀の初頭にかけて生存しておりました。これより前、僧侶階級と王族との間にはしばしば勢力争いから衝突があり、激烈な闘争が繰返されてきておったのであります。けれども釈迦出生の当時には王族が僧侶階級の強力な勢力に圧倒されておったのであります。
従って僧侶階級は他の全ての階級に君臨して、極度に自己の階級を尊大にし、終には自ら造物主と称えるようになったとされております。このような事態であったために、社会には多くの弊害が簇出(そうしゅつ)し、不正不義のために怨を呑んで死んでゆくものも決して少くなかったのであります。
要之(ようするに)、バラモン教が最大の権力を握ってしまった結果、その弊害が釈迦の頃になって、その極限に達していたのであります。そして最早何らかの社会的な革新がなされなければならない機運が充分に熟しておったのであります。しかも好都合なことには、釈迦は王族出身であった為めに古い宗教的な因習に捉われることなく新規の宗教観を唱道できたのであります。王族出身であるという点が、ナザレのイエスとは異っておりますけれども、その歴史的状況はあたかもイエスがユダヤ教僧侶の宿弊を根底から破壊してしまい、その当時の社会を大いに震撼させたのと非常によく似たところがあるではありませんか。
更に釈迦が唱道し始めてから、後年に至って仏教と称されるようになった当時の新興宗教が、以上のような在来の伝統宗教に対して示したその優越性は、実に教義の内容にあったのであります。それはまず平等主義に立脚して階級的差別を超越したこと、次に偏頗な氏族性を脱して普遍的な性質を有するようになったことなどであります。
釈迦は平等的な世界観をもっておったためからして、社会的にも平等主義を唱道して、当時のバラモン宗徒が主張しておったような意味での階級的な差別観を否定し、そして歴史的に成立してきた階級制度を破壊する上に予想外の効果をあげることが出来たのであります。
僧侶階級がどんなに絶大な勢力をもっておったとはいえ、数の上から言えば他の三つの階級が僧侶達より遥かに多かったことは容易に推測することができます。言い換えますと、釈迦の平等主義は社会の大多数の成員にとって都合の好い防禦であったのだし、彼らを苦難から救い出すべき唯一の警鐘でもあったわけなのであります。農商階級や奴隷階級は言うまでもなく、王族階級でさえも僧侶達からすれば劣等なのだと見なされておったのであります。ところがこれに反して、釈迦の説くところによれば、皆僧侶達と同等であって、何らの差別もないのであって、奴隷のような賎民達でさえも、今や僧侶達と優劣はないものとされたのであります。
このような一視同仁の聖者が現われて、学識のある者であろうと、又無学な者であろうと、そんなことは問わず、又貧富の差別もつけずに、どんな人でも愛し、また援けようとしたのでありますから、社会の大多数は震撼し始めて、遂に世界の大宗教になってゆく端緒を開くに至ったわけなのであります。この点でもまたイエスの叫んだ博愛精神を想い起こさせられずにはおりません。
また釈迦が偉大な影響を後世に及ぼした原因には、その普遍的な性質があずかって大いに力があったのだということを看過してはなりません。バラモン教は偏頗(へんぱ)な氏族的な、ないし種族的な性質をその特殊性としておりました。非常に排他的であったわけなのであります。それはインドのアーリアと称する血族の信仰だったのでありまして、その血族と連絡するものだったのであります。
換言すれば、バラモン教はインドのアーリアの宗教だったのでありまして、その儀式は専ら当時のバラモン僧侶達の管轄に属しておったのであります。でありますからインドアーリア以外の人間がバラモン教を信仰するということははなはだ意味のないことでもあったわけであります。
つまりこのバラモン教対釈迦の関係は、ちょうどユダヤ教対イエスの関係に極めて相似たものがあったのであります。ユダヤ教もまたユダヤ人の血族と連絡しておった信仰でありました。つまり種族的な、排他的な性質をもった宗教だったのであります。バラモン教はユダヤ教と同じように種族的な宗教であったために、インドアーリアの血液が身体に循環しているものでなければ、これを尊信することができなかったわけであります。従ってインドアーリア以外にこれを伝播することができず又何人もこれを伝播する必要を見なかったと考えられるのであります。
そんな意味からして、このバラモン教はインドアーリアの区域内に限られてしまったわけでありました。ところが、釈迦の唱道した仏教はそうではありませんでした。それが持っていたところの普遍的な性質のために、いかなる国土にも伝播することが出来ましたし、またいかなる国民もこれを信仰することが可能だったのであります。この点ででもイエスの説いた教えが、普遍的な性格を持っていったために欧州全土に伝播していたのと、その間の消息がよく似ております。
釈迦は特に武力を使ってバラモン教に反抗したり、僧侶達を圧倒したのではありませんでした。一切を同一視する大きな平和的な世界観によって、バラモン教とは相容れない一種の宗教を建設して、幾許(いくばく)もなく無数の信者を獲得していたのでありました。釈迦の教義に帰依したものはただ王族階級や農商階級、さては奴隷達ばかりに止まらず、当時の僧侶達でさえもこの新興宗教に改宗したものは少くなかったのであります。
当時はこんな風な情勢であったために、釈迦が出現してきたことはバラモンの宗徒にとっては実に一つの大きな脅威となったわけであります。僧侶達はかつて釈迦が出生してくる以前には王族階級を幾度か圧倒したこともありました。けれども今や無形の、精神上の戦いにおいて彼らはその王族階級から出でたる釈迦のために敗北したのであります。
釈迦の勢力は日に月に強大となって、あたかも燎原(りょうげん)の火のようであったのであります。そのためこれを遮るものがありませんでした。バラモンが以前の勢力を恢復して仏教の痕跡を中央インドから絶つようになったのは実に遠く紀元後九世紀頃の事だったのであります。
けれどもバラモンが釈迦の余勢をインドの中央から撲滅したと思ったときには既に、釈迦の感化は国境を超え、また民族を超えてインド以外の各国に広く普及し、バラモン教が到底匹敵することの出来ぬまでの大勢力を世界に占有してしまっておったのであります。