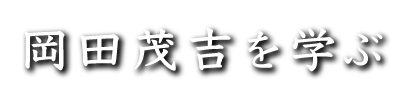「翠竹野雀」竹内栖鳳 昭和7~8年頃
昭和二十七年七月御垂示
七月一日
≪御垂示≫朝からは、初めてだから変ですね。
≪お伺い≫連日の来客で御疲れでは。
≪御垂示≫なんだか、性格が変わった様です。面白い様な、骨の折れる様な。
≪お伺い≫陳列品は時々御変えになられますので。
≪御垂示≫いいえ、連続です。秋に――十月に琳派展をやるつもりですが、それ迄変えないつもりです。どこの展覧会もそうです。幾月なら幾月と、そのままで通して、ちょいちょい変えるという事はないです。
≪お伺い≫昨日は佐藤朝山先生の猫が変わっておりましたが。
≪御垂示≫あれは、平櫛田中という人が来るので、どうしてもあの人の物を出さなければならないので――丁度ありましたから、変な人物を出したんです。田中さんが見て、これは少しひど過ぎる、今度はもっと良い物を出しましょうと言っていたそうです。
≪お伺い≫御招待の方は中々一流専門なので、言っている事を聞いてをりますと面白く、天狗が随分。
≪御垂示≫いや、ともかく天狗としては大したものです。
≪お伺い≫一休の讃には五、六名が非難しておりました。
≪御垂示≫もう変えました。私もあれは分かっているんです。
≪お伺い≫昨晩の宴会の席で長与博士が感想を述べ、来る迄はあんなに立派なものと思わなかったが、来て見てびっくりした。なんでも、批評すれば幾らでも出来るものだが、こういう事を実行したという事は敬服する。という様な意味の事を言っておりました。それから中川一政画伯は、現代物が非常に見劣りがすると言っておりました。大観でも栖鳳でも良いに違いないが、ああいう良い物の中に現代物はどうも――と言っておりました。
≪御垂示≫現代物を並べない方が良いと言うんですか。あの人は分からないんです。蒔絵は古いものより現代物の方が良いですよ。書画ですか――良いです。栖鳳なんかも良いです。古画に負けないです。栖鳳の竹なんか光琳に少しも負けませんよ。もっとも現代物の古径とか靭彦になると確かに負けますが、然し栖鳳、雅邦、大観――あれは負けていません。蒔絵は現代物の松哉は断然昔のより抜いてます。
≪お伺い≫因果経でエピソードがあります。この間中学校の教頭が来ましたが、益田さんの所で見たそうです。なんでも、信州の青年が、こんなものがあるが金になるかと持って来たので、益田さんが驚いて二万円やって、この金は他のものに使ってはいけないと言ってやったそうです。青年は無造作に持っていたそうです。
≪御垂示≫二百三十行あったのを幾つにも切ったんです。一巻が二百三十行です。一番長いのが八十四行。それから五十四行二つ。あとは三十行、十行と別けたんです。切った道具屋が私の所に来ます。
≪お伺い≫湯女は皆褒めてます。長与さんも松田さんも、一番推奨してました。
≪御垂示≫肉筆物では一番です。
≪お伺い≫浅野さんやその他の、見に来た人はみんな湯女を褒めてます。
≪御垂示≫そうでしょうね。
≪お伺い≫大体又兵衛より前だろうと言ってます。
≪御垂示≫私もそう思ってます。むしろ又兵衛はあれから影響を受けたんだろうと思います。あの時代は落款を入れないので分りません。又兵衛なんか、あれから余程経ってます。
≪お伺い≫昨日の久志さんというのは、陶器の研究家でございますか。
≪御垂示≫そうです。久志さんは、中々分かりますが、幾らか知ったかぶりという所があります。ちょっとこじつける所があります。
≪お伺い≫『美術工芸』によく書いてますが、随分口の悪い人で。
≪御垂示≫そうですね。元支那の公使館の何かをしていたんじゃないですか。官吏ですよ。
≪お伺い≫宗達は光琳より五、六十年前で。
≪御垂示≫もっとです。二百年位です。歴史が色々になってますが――二百年という説と百五十年という説とあります。とにかく百年以上は違います。
≪お伺い≫琳派という系統は抱一でお終いでございましょうか。
≪御垂示≫お終いでもない。抱一の弟子で其一というのがちょっとできます。其一の画帖は直さなければならないが、出します。空棚になった所があるでしょう。あそこに其一を出します。其一の次が明治時代の道一という人です。この人で終りです。それから、美術院というのは光琳を復活したというものです。岡倉天心の目的はそれです。光琳を現代に生かせというので、無線画を始めたんです。つまり光琳、宗達は無線画――線を省いたんです。美術院で光琳の無線画をやって、最初朦朧派という綽名をつけられて、それが馬鹿に人気を博したので、日本画はみんなそれを真似したんです。今の日本画はそういう意味になっていて、結局光琳が現代に来ているんです。最近はそれに油絵を採り入れたんです。
≪お伺い≫宗達より光琳がずっと上に御覧になっておられますので。
≪御垂示≫ずっと上とも言わないが、それに光琳は宗達の真似をしたんです。ああいった画き方は宗達が元祖です。ですから、物に依ってはどっちとも言えない。只光琳の方が絵に破綻がないです。宗達の方は未完成といった何があります。だから宗達は非常に良いのと悪いのがある。光琳にはそれがないです。悪いというのは滅多にないです。だから、結局光琳の方が上という事になります。
≪お伺い≫宗達の鶏は一般が非常に褒めます。
≪御垂示≫たらしこみというのは宗達が元祖です。あの、にじみ出たものです。今も真似してますが、たらしこみが最も良く出たのが鶏です。宗達の特色が一番良く出てますから、あれを出したんです。
≪お伺い≫雪舟も珍しいもので。
≪御垂示≫珍しいです。
≪お伺い≫褒めてました。
≪御垂示≫雪舟はもっと乱暴に画いてあるんです。ところがあれは実に入念に画いてあるんです。画き方が実に丁寧なんです。
≪お伺い≫武蔵の達磨も。
≪御垂示≫あれも良いです。
≪お伺い≫絵なんかには色々な議論が出てましたが、陶器類は非難の声は聞かず非常に褒めてますが、特に力を御入れになられたのでございますか。久志さんは非常に褒めてました。
≪御垂示≫あの人はその点は良く分かります。支那陶器を褒める人は確かです。他の人は分からないんです。けれどもあれ程分かっていても青磁は分からないです。青磁というのは難しいです。日本に青磁の分かる人はないです。みんな意見が違います。今日来る事になってますが小山富士夫という人、それから尾崎洵盛。尾崎さんが一番なんです。小山さんがその次で、久志という人が三番目なんです。尾崎さんと小山さんは、鑑識において、幾らか専門は違っているんです。久志という人と小山さんが、去年あたりから非常に喧嘩しているんですが、小山さんが負けそうなんです。どっちも支那の陶器や窯を研究してます、やっぱり天狗ですが――。支那の窯だけ研究しても分からないです。大変に数があるんです。
≪お伺い≫良いなと言う後に非常に理窟がつくのです。
≪御垂示≫そうです。それで断定が出来ないんです。だから一致する意見というのはないです。他のものはあっても、青磁だけは合わないです。それだけに青磁は難しいんです。しかし一番良い青磁の香炉――あれだけは非難する人は一人もないです。皆恐れ入ってます。だから、やっぱり本当に良い物は誰でも頭を下げます。あれは世界一です。支那陶器の中で、世界一の物が幾つもあります。青磁の良いのは米国や英国にも無いです。私位のものです。英国のデイビッドなんかは、青磁は大いに自慢している様ですが、それがみんな若いです。明以後のものです。私の所は青磁はほとんど宋です。
≪お伺い≫難しいのか、良いなと言って理窟は言いません。
≪御垂示≫分かる人はないんですから。
≪お伺い≫一休のは。
≪御垂示≫一休は最初から駄目なんです。一休の肖像が画いてあって、その隣が一寸大したものですが、私は気持が悪いので変えちゃいました。今度は一寸良い物を出しました。道風の継色紙というのを出しました。古筆もあんまりなかったのです。しかしそういう風に見てくれるという人があるという事は張り合いがあります。
≪お伺い≫布教者の立場と致しまして、メシヤ教を再認識して帰ってくれる事が一番嬉しく思います。
≪御垂示≫そうそう。新宗教に対して一番誤解している人に向って、美術館は一番でしょう。さもなければ、ああいう人達には効きっこないです。入ろうとしないです。やっぱり、ああいった専門なり学者というのは局部的で、全般的に見る人はほとんどないです。昨日の中村勝馬という画家が牧谿の双幅を非常に褒めてましたが、あの人は宋元画ではあれが一番良いんだ。宋元名画集でも牧谿のあれが一番好きで、今度本物を見せてもらって実に嬉しいと言ってましたが、やっぱりそれは間違っていないんです。吉屋信子なんか九谷が一番好きだそうです。一番最初に陶器を好きになるのは九谷なんです。それから進んで行くと支那陶器になる。それから本当に良いのは仁清ですが、仁清というのは世の中に無いから、そこで世の中の人は知らないです。仁清は日本陶器としては一番です。ですから、仁清を出したんです。
≪お伺い≫仁清の茶碗は褒めております。
≪御垂示≫あれは有名なものです。仁清の茶碗ではあれが一番です。
≪お伺い≫花車を引いているものというのは、変わっているので珍しがりますが、やはり茶碗が一番で。
≪御垂示≫そうですね。仁清の壺があると良いんですが、壺が無いんですよ。
≪お伺い≫得意なのでしょうか。
≪御垂示≫得意という程ではないが、大きいから見応えがあります。壺の良いのは、博物館の梅の壺です。長尾美術館の藤の壺、根津美術館の京都の吉野山の風景。この三つが良いんですが、これは買う事は出来ないんです。長尾のは一時売る様な話でしたが、あれを売っちゃうと呼び物が無くなっちゃうんです。ですからどうしてもあれだけは離さないです。ですから壺さえあれば、この美術館も天下無敵です。仁清の水指があったでしょう。あれでも大したものです。仁清と乾山は世の中にあんまり無いので、皆見ないから趣味が湧かないんです。乾山の鉢なんか見てくれなければしょうがない。吉野山、立田川とありますが、あれが大したものなんです。未だ、九谷や柿右衛門、鍋島を見る人は、陶器の方も素人からやっと何した位です。博物館に行っても、仏とかそういうものは知っている人がありますが、ああいったものはまことに無いです。見る所がないです。光琳、宗達は未だ色々ありますが、いずれ琳派展をやりますから、今みんな出さないで、なるべく出さない様にして取って置くんです。光琳なんかでも、未だすごいものがあります。去年博物館で開いた時は随分人気を呼びました。あの時はマチスと一緒でしたが。
文化財保護委員の富士川さんという人に琳派展を話したら、博物館の物ならどんな物でも自分が世話するからと言ってました。
≪お伺い≫木曾川上流の日本平に、乾山焼というのがありますが、字は違っております。
≪御垂示≫それは模倣物です。乾山の弟子とか、何代目とかいうのが、そこで焼き始めたんでしょう。初代の本当の乾山は、京都と江戸の根岸です。他には無いです。
≪お伺い≫栃木県に。
≪御垂示≫そんなのは聞きませんね。
≪お伺い≫栃木県の土を使ったと。
≪御垂示≫栃木県の土を使ったのでしょう。焼いたのは根岸です。
≪お伺い≫鶯谷の。
≪御垂示≫そうです。その子孫という事になっているんですか――とにかく縁はありますが、乾也というのがあります。明治時代に、根岸でやっていて向島に越して、乾山風のものを作った。簪玉が上手くて、乾也玉と言って、明治時代には非常に流行ったものです。古い女の人は知っていますよ。乾山は、学者が研究した結果間違えて、色を使ったのは乾山じゃないという説になって、博物館もその説を信じて、乾山の色絵物は博物館で出さないんです。今もって黒絵だけでしょう。近来になって、それは間違っているというので、大分色物の方に傾いて来ましたが、今となってはそういうものは博物館の手に入らなかったから無いんです。黒いものは、今私の所に色々あります。今度の琳派展の時に取って置きます。何時か北原君の所から持って来たんです。まだ持っているんですか。
≪お伺い≫どうでございましょうか。お茶席のお菓子皿でとても宜しいのがございましたが。
≪御垂示≫あれは良いです。