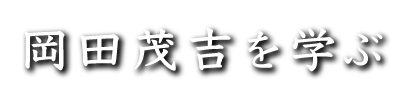Warning: Undefined array key "file" in /home/wp856168/meshiya.jp/public_html/wp-includes/media.php on line 1768

教団が新しい体制「世界救世(メシヤ)教」のもとに、それこそ日の出の勢いで救世の神業を開始してから二ヶ月たってのこと、熱海は二度の大火に見舞われた。一度は4月3日の午後、熱海駅近くの仲見世・商店街が火事になり、94軒を焼失し、さらのその10日後の13日には前回を上回る空前の大火となった。その日の夕方五時過ぎのこと、海岸近くの埋立地の一隅にあった建設会社の作業場から燃え上がった火は、おりからの強風にあおわれて、みるみるうちに燃え広がり、やがて熱海の中心街は火の海と化した。夜空を焦がすその様子は、遠く離れた湘南の鎌倉や大磯からも見ることができたといわれる。猛威を振るった火勢が町を横断してようやく衰え、市街西部の天神山の麓(ふもと)で鎮火したのは夜中の十二時に近かった。後の調査によれば焼失棟数979、焼失世帯1,461、被災者5,745名、被害総額30億円であった。
強風に加え、水の利の悪さが致命傷となり、地元の消防団も、早川、湯河原など近隣の町々から応援に駆けつけた団員らも、火勢のもの凄さに、有効な消火活動もできないまま、このような大惨事に立ちいたったのである。
直接の失火原因は、建設現場の労働者の捨てた煙草の吸い殻がガソリンに引火したからであるといわれている。
瑞雲郷の聖地建設現場では、この日も多くの奉仕隊員が職人と共に作業にあたっていた。当時すでに、現在の救世会館が建つている敷地と、その周囲の石垣、そして水晶殿の敷地といった瑞雲郷の基礎的な姿が、その形を現わしていた。
海岸の一角に上がった火の手は、海抜200メートルの瑞雲郷から、手に取るように眺めることができた。サイレンがものものしく鳴り、火事がただならぬ様相を見せ始めたころ、奉仕隊員らは火元に比較的近い清水町の仮本部を気づかって山を下った。彼らが仮本部に着いたころには、火の粉は雨のように降り注ぎ、仮本部に火が付くのは時間の問題と思われたほどであった。建物の中ではすでに神体が、教祖の揮豪した書とともに安全な場所へ運び出された。
教祖がよ志を伴い、水口町の碧雲荘から清水町へ来たのはそのころである。あわただしく荷物を運び出している人々にねぎらいの声をかけてから、教祖は火事に向かって、じっと浄霊をしたのである。
正門の扉に火がかかり、またたく間に焼け落ちたのはそれから間もなくのことである。荷物の運び出しはなお続いていたが、手のあいた者には、バケツや桶、鍋や洗面器などが配られ、あぶないと思われる場所へ手送りでリレー式に水が運ばれた。屋根から羽目板、壁にいたるまで絶えず水がかけられたが、猛烈な火勢のためにすぐに乾いてしまう。乾いてはかけ、乾いてはかけ、夢中で繰り返すその間にも火の粉は降り注ぎ、身体に付いた火の粉を振り払う間もない。そのうえ、屋根にもおびただしい火の粉が落ちかかる。まわりの家屋や商店は火を吹き、仮本部は三方を炎に囲まれ、庭木はすでに燃える葉もなくなった。隣接する光新聞社・出張所の建物はこの時ついに火に包まれた。一同は焼け付くような熱さを避けるために水をかぶり、池に入っては消火活動を続けたが、服はたちまち乾いて、今にも火を吹きそうになる。水の容器を持たない人々は屋根の上に立ち、迫ってくる炎に向かい、無我夢中で浄霊の手をかざした。いよいよ万事休す、と思われたその時である。にわかに風向きが変わった。今にも仮本部をのみ込むかと思われた火炎は、背後の方向へ押し戻される形となったのである。ときに火災発生から五時間を経た夜の十時ごろのことであった。
碧雲荘に帰った教祖のもとへ、仮本部の急を告げる知らせが次々と届いた。
「焼けました。」
「焼けています。」
しかし、教祖は少しも動ずるふうもなく、
「いや、焼けない」
ときっぱり言い放った。その様子は確信に満ち満ちている。その少し前であったが、火が銀座通りへ燃え移った時に、
「清水町も旭町もあぶないだろう。だから、みんなにそう言って避難準備にかかるようにしなさい。」
と指示した教祖であったが、また同時に絶対の守護を確信してのことであろう、
「仮本部だけは焼け残るだろう」
と言い切ったのであった。果たせるかな、火事は銀座から旭町、清水町へと広がり、誰もが類焼を免れまいと予想した仮本部は惨憺たる瓦礫の中に、無事焼け残ったのである。
奇跡はこのことばかりではなかった、翌朝、光新聞社・出張所の焼け跡を片付けていた奉仕者たちは不思議なものを掘り起こした。灰や焼け屑の中に半分燃え残った機関紙が発見されたのである。それは戦後初めて発行された『光』創刊号と改題後の五三号の『救世』であった。あれほどの猛烈な炎の中に新聞紙が燃え残っていたということに、みなはまず驚いた。それを掘り起こしてみて一同の驚きは、さらに畏敬の念へと変わった。というのは『光』創刊号の第一面には、紙面の半分を費して教祖の写真が掲載されていたが、火はちょうどその写真を避けるように、まわりだけを半円形に焼いて消えていたのである。『救世』五三号には、やはり第一面に教祖揮毫の大弥勒(みろく)像が掲載されていたが、それも焼け残っていた。作業にあたっていた人々は、みな手を休め、この新聞のまわりに集まり、込み上げてくる感動に涙を流したのである。
熱海大火におけるこの奇跡は、『救世』紙上に大きく報道された。宗教的な感動の渦は、その輪を大きく広げて、とかく新興宗教の信者として白眼視されることの多かった全国の信者に勇気と希望を与えたのである。