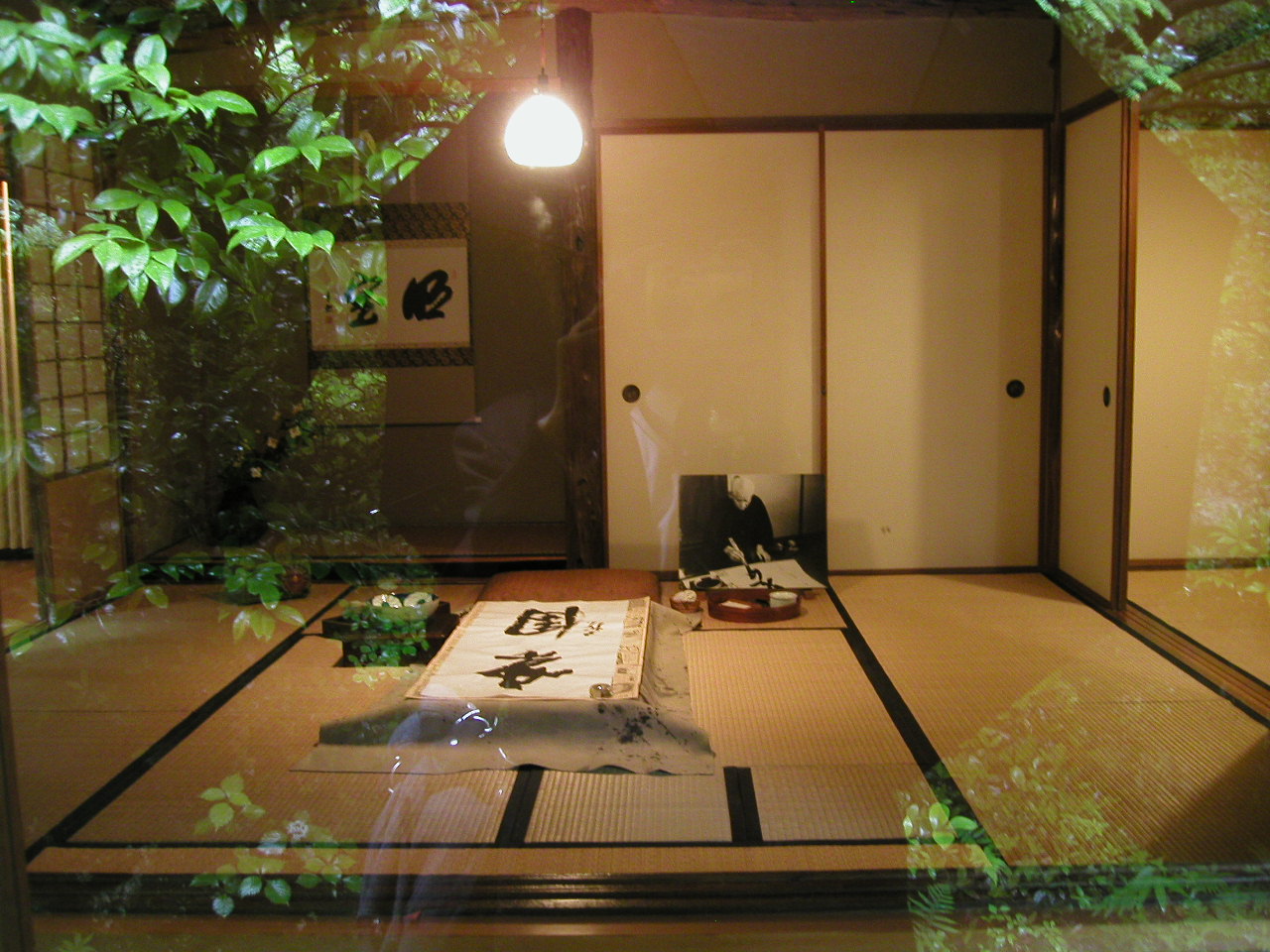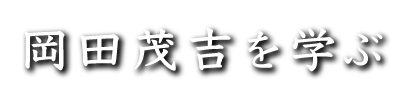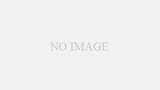それから美術について――これはいずれ小冊子にして美術館に来た人達にやろうと思ってますが、それを書き始めたのです。これは品物や何かについて、一つの予備知識として知って置く必要がある。これは書き始めですが、書けただけを読ませます。
(御論文「東洋美術雑観」)【註 栄光一六六号】
越州窯というのは一番古いのです。支那の室に入ると直ぐ右側に大きな壺があります。あれが越州窯の一番良いのです。あれは世界に一つしかありません。英国、米国にありますが、もっと小さい物です。あれだけの大きさで、あれだけの良い作というのは絶対に世界に無いのです。あれがつまり青磁の始まりなのです。
均窯――これも、真中に大きな皿があって、両側に水盤がありますが、この事です。二色のはっきりした物を出したのです。
梅瓶――これについては今博物館で展覧会をしてますが、今月の十日迄あります。そこに出品の二つが世界一です。アメリカのロサンゼルスで支那陶器の展覧会があって、日本から十五点出しましたが、この十五点の中でこの二つが一番良いのです。
白定窯――これも世界に無いです。真白な水指と徳利がありますが、水指の方は一寸形の変わったのは岩崎にありますが、徳利は日本には無いです。外国にも無いです。外国の物が、今度のロスアンゼルスの展覧会で何百と出たでしょうが、やはり日本の十五点というのが断然抜いているのです。あっちの新聞や雑誌に出たのも、日本の事が三分の二位出ていたそうです。だからここにある支那陶器だけでも、数は敵わないが、質から言ったら英国、米国に勝ってます。
これを分かって、そうして一つ一つ見ると面白いのです。まあ来る度に気長に見ていると段々分かって来ます。
それから、南蛮屏風という信長の時代に出来た物ですが、博物館の人が来て、明治三十八年から探しているのですが、どこに行っても所在が分からない。ここに来て分かって実に有難いと嬉しがって褒めてました。これと同じ物を細川さんが持っているのです。それが日本一とされていたのです。去年サンフランシスコの展覧会に出しましたが、よく見ると下書きがチョイチョイあるのです。どうもおかしいと思ったら、こちらのが元だというのです。これを真似た物に違いない。こちらのが本物で細川さんのがその写しという事が分かった。私の方のは非常に綺麗なのです。細川さんのは大分やつれている。それを聞いて私も非常に嬉しかったのです。